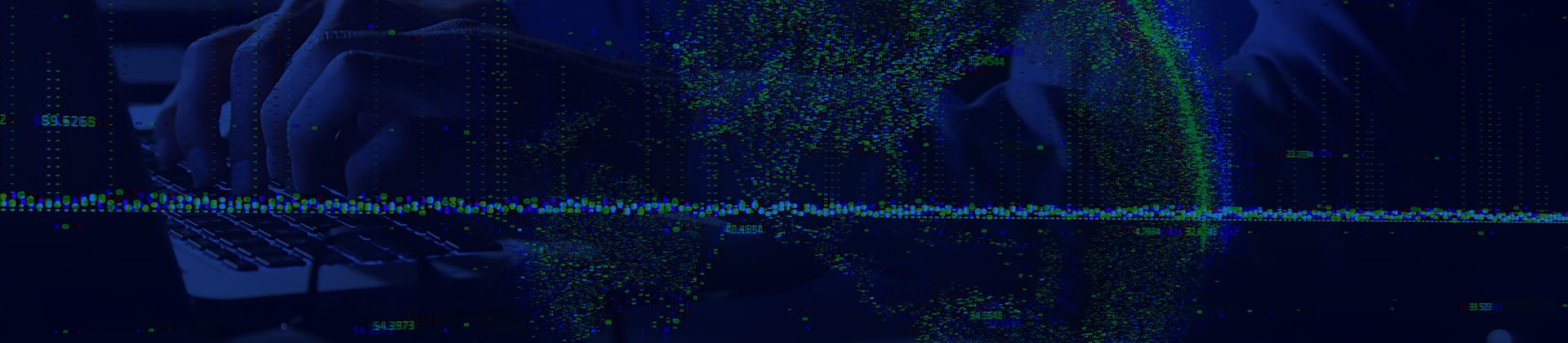はじめに
「ビジネスと人権」という主題は、近年、我が国を含む世界の企業にとって、避けては通れない重要な経営課題として認識されつつあります。この主題が国際的に注目された契機[1]となったのが、2011年に国連人権理事会が採択した「ビジネスと人権に関する指導原則」[2]であることはよく知られています。従来、人権尊重の主たる責任主体は国家とされていましたが、この「指導原則」では、国家に加えて民間企業にも、その事業活動およびバリューチェーンにおいて人権を尊重する責任があることを明記しています。この背景には、経済のグローバル化が進展し、企業が越境的な事業展開を進める中、その活動が国内外問わず、直接、間接に人権侵害に加担するケースが多発していた状況があったことが考えられます。
他方、「ビジネスと人権」という主題は、こうした人権尊重プロパーの文脈と同時に、いわゆる「サステナビリティ」、「エコノミック・ステイトクラフト」といった文脈とも密接に絡んでいることから、個々の企業としては、そうした関連する領域の動向も視野に入れつつ、自社の企業価値や成長可能性に直結する課題として、多面的な取り組みを求められているといえます。そこで本稿では、そうした複数の文脈が交差する「ビジネスと人権」という経営課題に対し、個々の企業としてどう向き合うべきか、そしてその際に求められる企業インテリジェンスはどうあるべきか、について考えてみたいと思います。
[1] 広義の「ビジネスと人権」をめぐる議論は1970年代からなされており、関連する国際文書として「ILO多国籍企業および社会政策に関する原則の三者宣言」(1977年)などがありますが、より具体的に企業と人権にかんする問題を取り扱い、また実効的な規範性を持つ文書としてこの「指導原則」は注目に値します。
[2] https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100165917.pdf
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の精神
今日、「ビジネスと人権」をめぐる実効的な規範性を有する国際文書として定着した感のある「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、「指導原則」)ですが、その採択に至るまでには国連内部でも紆余曲折があったとされています。とくに2003年に国連人権小委員会が採択した「人権に関する多国籍企業および他の企業の責任に関する規範」(以下、「規範」)という文書が「失敗」に終わり、その反省に立って「指導原則」が策定されたことは注目に値します。「規範」では、企業に対して国家と同水準の人権の尊重・保護義務を、国際法の下で直接に企業に課そうとしたところ、その高い要求内容に当惑する経済界と歓迎する人権活動団体の間に「埋めることのできない溝」(「指導原則」序文の表現)が生じたとされています。「規範」の問題点として、「ビジネスと人権」をめぐるさまざまなステークホルダー(国家、企業、労働組合、市民社会、投資家など)の期待と行動が収束しうる「権威あるフォーカルポイント」が欠如していた点が指摘されている中、「指導原則」では、特定のステークホルダーにだけ過剰な義務や負担を負わせる取り組みではなく、各ステークホルダーが受容し、持続的に関与できる取り組みを定めるよう設計されたことが窺えます。
なお、この「指導原則」を受けて、各国政府は、具体的な対応に向けた国別行動計画の策定や関連法の整備等を進めています。我が国でも、2020年10月、「ビジネスと人権に関する行動計画」が制定されたほか、2022年9月には、経済産業省が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表しています[1]。
[1] https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003.html
人権デューデリジェンス—PDCAサイクルとしての取り組み
「指導原則」の内容は、「人権[1]を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」、「救済へのアクセス」の3つの柱から成ります。国家に対しては「義務」を課し、企業に対しては「責任」を求めている点が特徴です。その中で、企業に求められる具体的な取り組みは以下の3点に大別されます。
- 人権方針の策定
- 人権デューデリジェンスの実施
- 救済メカニズムの構築
これら3つの取り組みのうち、企業にとって中心的な課題となるのが②「人権デューデリジェンス」です。以下、その具体的な内容についてご説明したいと思いますが、その前に①「人権方針の策定」と③「救済メカニズムの構築」についても簡単に触れておきたいと思います。
まず「人権方針の策定」とは、企業として、人権を尊重する責任を果たすというコミットメントを発信することを指します。つぎに「救済メカニズムの構築」とは、企業が人権への負の影響を引き起こし、又はそれを助長していることを確認した場合、企業は正当な手続を通じて救済を提供する、又はそれに協力することを指します。人権上、負の影響を受けた個人あるいは地域社会が活用できる苦情処理メカニズム(グリーバンス・メカニズム)がここでいう「救済メカニズム」となります。
さて、「人権デューデリジェンスの実施」とは、企業として、人権への影響を特定し、予防または軽減し、どのように対処するかを説明するために、人権への負の影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する情報発信を実施することを指します。
人権デューデリジェンス(DD)の具体的な作業工程については、「指導原則」の18から21で説明されているところ、その詳細は図1のとおりです。
| 図1:人権DDの作業工程 |
重要なことは、人権デューデリジェンスが、たとえば企業のM&Aなどで行う各種のDDとは異なる意味を持つという点です。
| 出所:『ビジネスと人権とは? ビジネスと人権に関する指導原則』(外務省、2020年3月) |
M&AにおけるDDは、取引先についてさまざまな経営リスクを把握するために行う一回的な調査を指しますが、人権DDは、企業が関与するさまざまなステークホルダーに対する人権上の負の影響を把握し、その予防や軽減のために適切な措置をとり、その内容を公表し、効果を検証するといった一連のプロセスを継続的・循環的に実施することが想定されています[2]。その意味で、人権DDでいう「デューデリジェンス」とは、本来的な「当然の義務(due diligence)」に近い含意があるといえます[3]。
このように「指導原則」に示された人権DDの作業工程は、「責任ある企業行動のためのOECDデュー・デリジェンス・ガイダンス」(2011年)でも踏襲されており、その流れは、企業の品質管理や業務管理でいうところの「PDCAサイクル」(Plan→ Do→ Check→ Actのプロセスを繰り返す)と近似します(下記、図2を参照)。
| 図2:人権DDのPDCAサイクル |
| 出所:OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct(引用は日本語版より) |
もっとも、一口に人権DDといっても、自社の労務問題から、取引先、バリューチェーンにおける人権リスク、地域社会における人権上の摩擦など、対象となる人権課題は多岐にわたり、地理的にも広範なスコープが要求されることは確かです。また、企業の規模や業容に応じて、留意すべき人権課題も異なってきます。したがって個々の企業としては、その事業ポートフォリオに即した、個別具体的な人権リスクマッピングを行った上で、優先度の高いリスク領域を特定することが重要となります。優先度は、リスクの深刻さ(生命に関わるものが最優先、影響を受ける人数の多寡、是正の困難さなどから総合的に評価)に応じて定めます。
なお、人権DDには、平時と有事の区別があります。上記で述べた内容はおおむね平時における人権DDの作業内容ですが、有事においては「強化された人権DD(heightened due diligence)」を実施すべきとされています。「強化された人権DD」とは、たとえば、「企業が事業を行う紛争等の影響を受ける地域の状況についての理解を深め、紛争等を助長する潜在的な要因等を特定することを通して、事業活動が人権への負の影響を与えないようにするだけでなく、紛争等の影響を受ける地域における暴力を助長しないようにする取組」などを指します(既述の経産省による「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」4.1.2.4を参照)。
[1] 「指導原則」でいう「人権」とは、「国際人権章典」や「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言」に規定されている、「国際的に認められた人権」を意味します。
[2] M&Aにおいて買収検討先が抱える人権リスクの有無を把握することを「人権DD」と呼ぶこともありますが、これは「指導原則」に定められた人権DDとは区別して扱う必要があります。
[3] 「デューデリジェンス」の語義の変遷についてはJPR&Cアナリスト・レポート第8号をご参照ください。
サステナビリティと人権
このように2011年の国連の「指導原則」を端緒として普及した「ビジネスと人権」をめぐる取り組みですが、関連するいくつかの主題との連携あるいは共鳴がみられます。その1つに「サステナビリティ」があります。サステナビリティは、広範な概念であり、その全容を本稿で取り扱うことはしませんが、ここでは近年、注目を集めつつある「コーポレート・サステナビリティ」について取り上げたいと思います。この概念は、端的にいえば、中長期的視点から企業が持続的発展や、その企業価値の継続的な向上を図ることを意味します。この「コーポレート・サステナビリティ」を可能とするのが、いわゆる「サステナビリティ経営」です。その指針となるのがESGへの対応です。
ESGを構成する「環境、社会、企業統治」はいずれも人権に直結する領域といえます。たとえば「環境(E)」問題のなかでも重要度の高い気候変動は、人命に直結する問題である上に、その影響により移住を余儀なくされた人々(気候難民)が人身売買や強制労働などの犠牲になる可能性も高いことから、深刻な人権課題につながるものといえます。「社会(S)」については、ダイバーシティ、労働問題、所得格差など企業の労務問題と重なる課題が少なくありません。「企業統治(G)」については、ステークホルダーの権利保護、社会的な負の影響など、「指導原則」が対象とする人権問題との関連性が高い領域といえます。
こうしたESGの視点を取り入れたESG投資あるいはESG経営は、ともに「環境、社会、企業統治」の各領域をめぐる諸問題の改善や解決につながるのみならず、いわゆる「人的資本」の価値向上や、そうした取り組みに注力する企業の価値向上にも資することから、企業にとって、単なるコンプライアンス対応(守り)としてのESG対応のみならず、企業価値の向上を視野に入れた積極的なESG戦略(攻め)へと発想を転換することが有益といえるでしょう。
エコノミック・ステイトクラフトと人権
「ビジネスと人権」との連携あるいは共鳴がみられるもう1つの主題として「エコノミック・ステイトクラフト(economic statecraft)」を挙げたいと思います。「エコノミック・ステイトクラフト(ES)」とは、国家が自らの戦略的目標を追求するために、軍事的な圧力ではなく経済的な手段によって他国に対して影響力を行使し、何らかの結果を導き出そうとする行動を指します。ESと人権の関係は、複雑かつ射程が広い問題であり、その全容を説明することは容易ではありませんが、さしあたり以下では、「米中対立と人権」および「EUの世界戦略と人権」という2つの観点からの事例紹をご介するに留めたいと思います。
- 米中対立と人権
いわゆる米中対立は、大局的には、第二次世界大戦後の民主主義と自由主義経済を基調とする国際秩序の中心的かつ実質的な担い手であった米国と、欧米等の先進民主主義国とは異なる政治経済体制を持ちつつ急速に大国化してきた中国との地政学上および安全保障上の利害の衝突が背景にあるといえます。たとえばバイデン政権は、2022年に発表した「国家安全保障戦略」において、中国を「世界秩序を再編する意図と、それを成し遂げるための経済・外交・軍事・技術力とを併せ持つ唯一の競争相手」と定めており、その中国との競争を優位に進めることが、米国にとっての「地球規模の優先課題」であるとしていますが、ここに挙げられた「経済・外交・軍事・技術力」のすべての領域において現在、米中間で戦略的な競争が展開されているなか、とりわけ「ビジネスと人権」の文脈に関連するのが、米国の安全保障に直結する技術覇権およびそれに付随するサプライチェーンをめぐる競争で、主として輸出管理の分野においてです。
米国はたとえば「ウイグル強制労働防止法」(2021年3月)および同法に基づく輸入禁止措置(2022年6月)によって新疆ウイグル自治区で生産された製品の輸入を原則禁止するほか、2023年3月には、「輸出管理規制(EAR)」が改訂され、輸出審査時等に考慮される「米国の国家安全保障または外交政策上の利益」に、「世界中での人権保護」を含めることが明確化されています。また多国間の取り組みとして「輸出管理・人権イニシアチブ」(2021年12月)およびその行動規範(2023年3月) の策定を主導し、中国を念頭に、デュアルユース製品が人権侵害に用いられないよう有志国で協力する体制を強化しています。
エコノミック・ステイトクラフトの性格が色濃いこれらの米国の取り組みには、民主主義の価値観の普及(人権擁護を含む)という理念的次元に加えて、中国に対する自国の技術的優位性の確保、特定分野におけるサプライチェーンからの中国の排除といった国益追及の次元など複合的な戦略的目標が組み合わさっているといえます。
- 欧州の世界戦略と人権
欧州(EU)は、環境(主として脱炭素化と気候変動)、デジタル、人権、安全などの領域に関わる国際的なルールや標準を形成し、域外にも普及させる志向を持つことから、「グローバルな規制パワー」と称されることがあります。
こうしたEUの国際的な影響力を「ブリュッセル効果」と呼ぶことがあります(米コロンビア大学の国際法・国際機構論の教授アニュ・ブラッドフォードが提唱した概念)。
| 出所:2023年3月1日付『日本経済新聞』記事「EUの影響力と課題(上)国際的な規制パワーに功罪」(著者:庄司克宏・中央大学教授)より |
| 図3:ブリュッセル効果のメカニズム |
EUは巨大かつ非弾力的な市場を抱えており、世界の多くの多国籍企業への大きな誘因力を有しています。そこで、EUが域内市場にその志向する価値を内蔵した高基準の規制を敷いた場合、多国籍企業としては、その基準に見合ったEU向け製品を製造するのみならず、同基準で他市場向け製品も製造したほうがコスト面で合理的となり、そこでそうした企業は、自国や他国にもEU基準の採択を働きかけることになります。その結果、EUはなんら強制力を発揮することなく、市場原理と多国籍企業の利益追求の姿勢を活用することによって、EU基準を一方的にグローバル市場に普及させることができる。単純化するとこれが「ブリュッセル効果」の概要です(図3を参照)。これは欧州が駆使する大規模なエコノミック・ステイトクラフト(ES)ということができます。
「ビジネスと人権」の文脈でも「ブリュッセル効果」は見て取れます。EUは、2023年1月、大企業にESGなどの非財務情報の開示を求めていた従来の「非財務情報開示指令/NFRD」を改正した「企業サステナビリティ報告指令/CSRD」を発効させ、ESG関連分野にかんするサステナビリティ事項の報告義務を強化しました。ESRSでは、ESGの3分野について、NFRDを越えた開示基準を設けています。
このほかEUは、2023年6月に、「企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令/CS3D)」のドラフトを採択しています。同ドラフトは、「自社、子会社及び“確立したビジネス関係を築いているバリューチェーン」における人権・環境デューデリジェンスの実施を義務づけた内容で、現在、欧州委員会、欧州議会、欧州理事会間での三者協議などを通じて検討が進められているところです。
これらCSRDやCS3Dは、いずれも欧州で事業展開する日本企業にも適用される可能性が高く(具体的な適用基準、適用時期については、高度に技術的な解釈が求められますが、紙面の制限上、本稿では省略します)、また、上記の「ブリュッセル効果」を通じて、欧州域外でも同様の取り組みが普及する可能性も否めません。
なお欧州では、国別に、英国が2015年に「現代奴隷法」を、フランスが2017年に「企業注意義務法」を、ドイツが2023年1月に「サプライチェーン・デューデリジェンス法」をそれぞれ制定しています。
コンプライアンス対応を越えた経営戦略を
日本貿易振興機構(ジェトロ)が2023年4月に公表した「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」[1]の結果によると、「人権DDを実施している」と回答した企業は全体の10%ほどで、「実施していないが、数年以内に実施を検討している」と回答した企業が約40%、約半数の企業が「実施する予定はない」と回答したとされています。
こうした数字から判断する限り、我が国の多くの企業が、現時点では、積極的に「ビジネスと人権」をその企業戦略に位置付けていない印象が窺えます。その理由や背景は、個々の企業によってさまざまであると思われますが、1つには「ビジネスと人権は戦略的な経営課題だと聞いたりするが、対応コストをかけてでもやっていく必要があるのか」という「もっともな疑問」が社内に根強くあるという点が考えられます。実際、多くの企業において、人権DDの担当部門は、人的リソースも限定されている中、迂遠な作業を手探りで進めながらも、非財務的な取り組みゆえに効果が見えづらい中で、「費用対効果に見合っていない」との社内評価に直面しているといったケースが少なくないかもしれません。
この点に関連して参考となるのが、2023年7月に経済産業省が取りまとめた「サステナビリティ関連データの効率的な収集及び戦略的活用に関する報告書(中間整理)」[2]です。この報告書では、「多くの企業では、開示要請や法規制への対応がサステナビリティ関連のデータ・情報の主な収集目的となっており(中略)経営戦略(進捗モニタリング、分析、経営の意思決定等)に活用するという発想にまではまだ至っていない」として、人権DDを含むサステナビリティ関連分野のデータが社内に「死蔵」されている状況を指摘しています。
本稿でみてきたように、「ビジネスと人権」という主題は、企業が関係するさまざまなステークホルダーに対する人権上の負の影響を予防・軽減するという中核的な目的に加えて、ESGの視点から企業の持続可能な成長を後押しするサステナブル経営、また米国や欧州などがエコノミック・ステイトクラフトを通じて展開する人権尊重の姿勢、など複数の主題が交錯するきわめて戦略的な経営課題といえます。
上記「報告書」では、「『開示』・『規制対応』・『経営戦略』は、それぞれ独立したものではなく、企業価値を高めることにおいては、それぞれがつながっている」として、それらの三位一体での積極的活用を推奨しています。ESG投資時代の自社の「先行者利益」を確保するためにも、「負担」を「機会創出」へとどう組み替えるかが、企業インテリジェンスにとって大きなチャレンジになるといえます。
[1] https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0303/9cfcf53ac729103f.html
[2] 2022年12月に経済産業省が「非財務情報の開示指針研究会」に設置した「サステナブルな企業価値創造に向けたサステナビリティ関連データの効率的な収集と戦略的活用に関するワーキング・グループ」における検討結果をまとめたもの。
この記事の執筆者