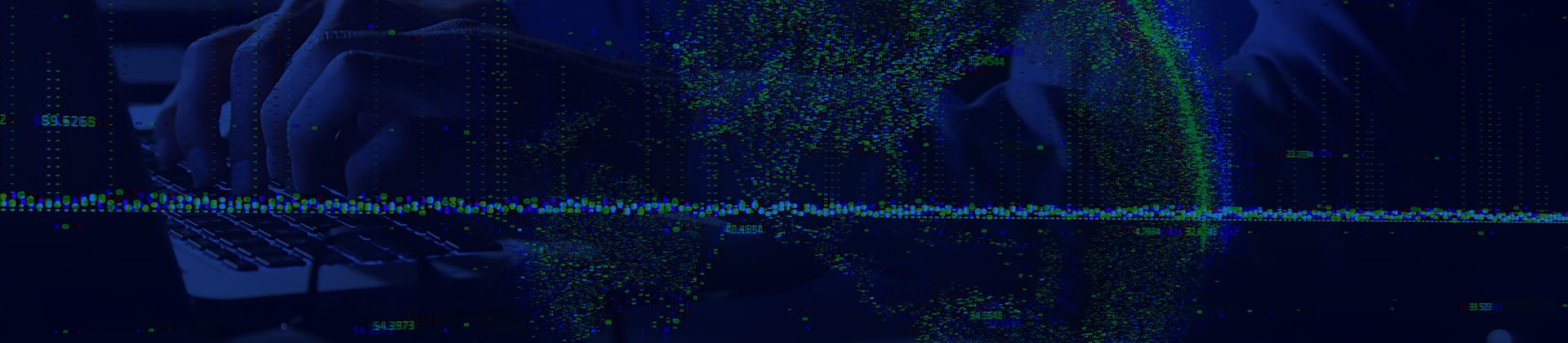はじめに
予測不能なことが次々と起きる現代世界。そのなかで民間企業は、さまざまな不測の事態に備えつつ、企業価値を守り、あるいは高めるための「企業インテリジェンス(corporate intelligence)」の強化をこれまで以上に求められるようになりました。孫子の有名な言葉、「名君賢将の動きて人に勝ち、成功、衆に出ずる所以のものは、先知なり」[1]は、21世紀の企業経営にも重要な示唆を与えてくれています。
ところで、一口に「企業インテリジェンス」といっても、その目的(経営戦略の策定、商取引の最適化、現場でのリスク対応など)に応じて、必要となる情報収集・情報分析の「手法」や取り組むべき「課題」は実に様々です。今回は、企業インテリジェンスのなかでも、特に切迫性のあるインシデント対応時に採用されることの多い「行動調査」についてご紹介します。
[1] 孫子の『兵法』、「用間篇 十三」にある言葉。現代語訳は、「名君、賢将と言われる人が戦えば勝って成功するのは、敵よりも早く情報を制するからである」。
1.行動調査とは何か
行動調査は、OSINT(Open Source Intelligence:公開情報に基づく調査)、HUMINT(Human Intelligence:人的情報源を介して行う調査)などのインテリジェンスにおける代表的な手法と比べると、一般的には、あまりなじみのない調査手法かもしれません。
行動調査は、英語ではPhysical Surveillance(PS)と表現しますが、たとえば、英語圏におけるこの調査手法に関する最もスタンダードな解説書として知られるFundamentals of Physical Surveillance(行動調査の基本)では、PSについて「情報収集を目的として、人物、車両、あるいは特定の場所で起きている活動を直接観察すること」と説明されています。
この説明は、行動調査の本質を端的に示しており、政府の諜報機関・法執行機関が実施する行動調査にも、民間企業が実施する行動調査にも当てはまります。
ただし、民間企業が実施する行動調査が、実際にどのような場面でどのように行われているのかについては、具体的に想像がつきにくいことはたしかです。そしてまず多くの人が、「民間が対象本人の同意を得ずにそのような調査を実施することに問題はないのか?」と思うかもしれません。個人情報保護やプライバシー、人権への意識が高まる昨今においてこれは非常に重要な問いです。
行動調査が法的あるいは倫理的側面から許容されるものなのか、そして実際の可否判断や実施時の調査設計等について、近時の事例も交え考察を行います。
2.法的観点
日本の民間における行動調査は、都道府県公安委員会に届出をした探偵業者によって行われています。探偵業務の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的に制定された「探偵業の業務の適正化に関する法律」(2007年6月1日施行、所管は内閣府)に基づいた業務を行うことが義務づけられているほか、各法令(個人情報保護法や民法、刑法など)に基づくルールに則り、プライバシーや人権の侵害を避けるために十分な配慮が必要とされています。
ここで重要となるのが、行動調査を実施する「必要性と合理性」です。プライバシーや人権侵害に繋がる恐れのあるセンシティブな手法の採用可否においては、事案の背景や目的、戦略等に即し、それが必要性や合理性を欠く恣意的なものではないか、あるいは過剰なものではないかなどについて、冷静に判断する必要があります。それがどのような事案であれば「必要性と合理性」が認められるのかについて、明確な基準やガイドラインは現状存在せず、最終的には依頼者が個別に判断する必要があります(専門家と十分に協議し、そのプロセスを記録しておくことが望ましい)。
また、行動調査の実施者においては、法令に抵触する行為(私有地への不法侵入、GPSを利用した監視など)を避けることはもちろん、調査依頼が不当な目的によるものではないか(違法行為の幇助とならないか、国外の諜報機関から利用されていないかなど)、慎重に判断することが求められます。
欧米諸国の多くでは探偵業者のライセンス制が整備されており、相応の条件を満たした者が定期的なライセンス更新や教育プログラムを課せられることで、信頼性が担保され、社会的地位も確立されている一方、日本では最低限のバックグラウンドチェック(犯歴確認など)のみの届出制となっており、業者の経験やスキルは千差万別で、社会的地位も確立されていないのが現状です。
行動調査を国内の探偵業者に相談する際には、上記のような法的観点について十分な見識を有し、調査の「必要性と合理性」についての見解や、適切な調査設計を提示してくれる業者であるか否か、慎重に選択することが求められます。
3.倫理的観点
倫理的観点から行動調査を考える時、日米の違いを知ることが示唆を与えます。上記のようなライセンス制と届出制という制度上の違い、社会的役割の違いには、日米の社会的・文化的な違い、特に個人情報保護やプライバシー、情報公開などに対する捉え方の違いが作用していると考えられます。
米国では州によって異なりますが、多くの場合は「私立探偵」としての立場が法的に認められており、民事訴訟や刑事事件の証拠収集を含む広範囲の調査を行うことができます。これは、米国では個人情報保護やプライバシーに対する厳格さが比較的低い一方で、表現の自由や情報公開が重視されており、個々が自ら情報を取得し、それによって自身の安全や権利を守るという意識が強く(例えば、公開されている犯罪者情報を得ることで自身を防衛するなど)、その情報取得(またはそのための手続き)をサポートする社会的役割として、「私立探偵」の存在が認知されていると考えられます。逆に日本では、個人情報保護やプライバシー保護の視点がより強調され、情報公開は限定的であり、自助の範囲は狭く、行政や司法に委ねる範囲が広いと考えられ、つまり探偵業者の社会的役割も限定的ということになります。
行動調査が倫理的観点から許容されるのかとの問いに対しては、上記のような各国の社会システムを踏まえた上で、自社の利益が行政や司法によって十分に保護されうる事案なのか、あるいは自社の利益を守るには(または社会的責任を果たすには)一定の自助がなければ困難な事案なのかなど、漠然とした印象論のみで是非を判断するのではなく、各事案の背景や目的、戦略等に照らし、個別に判断する必要があります。
4.実施事例
ここまで、法的・倫理的観点から行動調査に関する概念的な考察を示しましたが、次に実際の実施例を挙げてみましょう。従来より日本の民間企業では、保険金詐欺事案、労災保険詐欺事案、従業員不就労事案などが、行動調査の実施頻度の高い事案として挙げられますが、社会情勢の変化に伴い、昨今ではそのほかにも多様な活用シーンが生じています。以下、複数の実施例がある不正関連事案、特殊株主関連事案、加えてM&Aやサプライチェーンマネジメント(SCM)におけるデューデリジェンス(DD)の一環として実施された事案について例示します。
- 社内不正に関する事例(A社)
内部告発により社員の業務上横領の嫌疑が生じた事案において、水面下で対象者のメールレビューや関係部署へのヒアリング等、社内調査を進めるが、対象者から疑いを認める発言を得る(あるいは刑事告訴を検討する)には、裏付けとなる情報が不足していた。A社は水面下の社内調査でこれ以上の情報収集は困難と判断し、担当弁護士との協議の上、一定期間の対象者の行動調査を検討。対象者が、共謀が疑われる外部業者と私的に接触していないか、また、生活状況に著しい変化(使用車が高額なものに変わっているなど)がないかを確認することを目的に実施するに至った。
これによりいくつかの状況証拠を得た後、A社は担当弁護士同席の下、対象者へ聴取を実行。その結果部分的に疑いを認める発言を得るに至り、会社貸与のPC解析や外部業者へのヒアリングなど、さらなる調査へと展開した。また、対象者への聴取後も、一定期間の行動調査を実施。これは対象者の逃亡や、身体・生命の危険を防止する観点から行われた。
このほか、類似の事案として、元社員の機密情報持ち出しの嫌疑が生じた事案において、元社員の競合他社への転職の事実確認や、不当な営業活動の実態を確認することを目的に行動調査が実施されたケースがある。
- 「特殊株主」に関する事例(B社)
反市場勢力と疑われる複数の株主について、各株主の素性や相互関係を把握する必要が生じた事案において、OSINT、HUMINTなどによるバックグラウンド調査を受託。その結果、対象となる個々の株主の素性や、彼らの相互関係は一定程度、把握されたものの、主導的立場にあると疑われる人物(非株主)との関係性が不透明なままとなった。そこで、B社および担当弁護士等との協議の上、当該人物と対象株主らとの関係性を把握することを目的に、当該人物について一定期間の行動調査(立ち寄り先や接触者の確認)を実施するに至った。
その結果、当該人物と対象株主らが会合場所としている拠点を確認。当該人物と対象株主らが密接に関係していることの蓋然性を高める重要な情報となった。
- M&AやSCMにおけるDDの一環として実施された事例
- M&Aにおいて、買収検討先(製造業)の経営トップの素行や交友関係に関する悪評、経営資源の私的流用への疑義などが浮上したケース。OSINTやHUMINTによるバックグラウンドやレピュテーションの把握のみでは評価が難しく、物理的に実態を確認する必要性が高いと判断、日時を限定した行動調査を実施。
- M&Aにおいて、買収検討企業(建設業)が雇用する外国人技能実習生らの労働環境や生活環境について、実態を確認したいとの要望があったケース。物理的な確認が不可欠と判断し、可能な範囲で建設現場における外国人技能実習生らの状況、および居住先(住環境)の観察を実施。
- SMCにおいて、業務委託先および再委託先(産廃処理業者)が不法投棄などの不適切処理を行っていないか確認する必要が生じたケース。地域住民へのインタビュー調査とともに物理的な確認が必要と判断し、実際に運搬ルートや運搬先の確認を実施。
上記いずれの事例においても、行動調査の可否判断においては、その「必要性と合理性」について、依頼者と調査受託者、あるいは弁護士を交え、十分な協議が行われたことはもちろん、物理的な調査以外に有益な情報が得る手立てがないという「非代替性」が共通して存在することにも注目すべきです。物理的に人を監視または追跡するというセンシティブな手法を検討する際には、その前段階として、OSINT、HUMINTなど別の手法の実効性について十分に検証することが必要であり、その上で行動調査以外では代替が難しいと判断された場合において、それを実行に移すことが望ましいと考えられます。
また、近時の傾向として、OSINTとの連携により、行動調査をより効果的、効率的に行えるケースが増加しています。高度なSNS分析等により、対象者の行動範囲や行動パターン、交友関係などを事前に、あるいはリアルタイムに把握することができ、それをインプットすることで、行動調査に割く時間やコストを最適化できるケースが増えています。
5.有効性
行動調査の有効性については、上記実施事例にもあるように、物理的な証拠を伴った客観性・真実性の高い情報を得られる可能性があり、それが交渉を優位に進めるための重要なカードとなるケースや、裁判での証拠として採用されるケースがあります。また、リアルタイムな情報が得られるという特性から、状況に応じた迅速な対応策(先手のアクションやカウンターの準備など)を講じることを可能にするという効果もあります。
このような有効性が発揮されたケースでは、決裁者(経営層)、プロジェクト責任者(担当部門)、あるいは外部専門家(弁護士、FA、IR・PR会社など)が、問題解決に至るまでの戦略を立案、遂行するプロセスの中で、当社を情報収集・分析の専門家としてアサインしたケースが多く見られます。これは、「行動調査」を単体として実行するのではなく、プロジェクト責任者や戦略策定者とのチーム連携の中でより戦略的に実行されることにより、その有効性が最大化されることを示しています。具体的には、行動調査の目的や方針の理解、調査状況の適宜共有、戦略の軌道修正への即時対応、情報の活用方法に関するコンセンサスなどが、チーム連携の中で円滑に行われることを指します。
他方、連携の不足が有効性を大きく阻害したケースも存在します。依頼者と調査受託者の間で調査の目的や方針の擦り合わせが十分に行われていないため、調査に費やす時間やコストを無駄にしたり、重要な情報を取りこぼしたりしてしまうケースです。
行動調査は、人間の行動や偶発的事象に結果が左右されるという手法の性質上、必ず期待通りの結果が得られるとは限らない側面もあり、許容される時間やコストとの兼ね合いからも、いかにして有効性を最大化するのかという視点は非常に重要となります。行動調査の有効性が発揮され、戦略に即したクリティカルな情報を得るために、どのようなプロセスやコミュニケーションが必要であるのか、過去の事例や専門家の経験則が示唆を与えるでしょう。
6.今後の展望
行動調査の実施については、その性質上、特に高い秘匿性の下で行われることが通常であり、実施件数や活用シーンに関する横断的な統計資料などは存在しません。
個人情報保護やプライバシーに対する世界的な意識の高まりを受け、日本においてもさらに厳格化が進行するとすれば、自助の範囲は一層狭まり、それに伴い探偵的な手法を用いる場面も減少するようにも思われます。実際に、このような社会環境の変化に伴い、許容される探偵的な手法や得られる情報の範囲は徐々に縮小しており、それにより調査現場の様相も一昔前とは大きく変化しているのが現状です。
他方、当社JPリサーチ&コンサルティングでは、行動調査を用いた案件数の推移は近時増加傾向にあり、これは戦略的な情報収集の一手法としての有効性や絶対的なニーズがある一方、機微な情報を共有する相手として、信頼に値する調査会社が減少または増えていないことを意味するものとも理解しております。
なお、実際に不正や企業間紛争時などにおける特定の状況下では、行動調査の活用が先鋭化しています。
この背景には、個人情報保護やプライバシーの厳格化とともに、情報収集の困難性が増す一方で、経済のグローバル化、人材の流動化、経済安全保障への対応、内部統制開示強化など、多様化・複雑化する社会環境に対峙するために求められる独自のインテリジェンス機能に対する意識の高まりが潜在しているとも考えられます。
今回は企業インテリジェンスにおける「手法」のひとつである行動調査に関する考察を行いました。企業が直面する様々なリスクに対し、実効性のあるインテリジェンスを発揮するとき、場合によっては行動調査という選択肢を検討する場面が訪れるかもしれません。
その際は、上記のような法的・倫理的観点を踏まえ、その「必要性と合理性」「非代替性」あるいは「有効性」について、事案の背景や目的、戦略等に即した十分な協議を行った上で、実施の可否判断を行うことが求められます。
特殊性が高い分野のため、実際の調査設計や実務レベルの詳細までを正確に記した著作物やインターネット情報は断片的に存在する程度で、個人向けの集客目的のものなど偏った内容も多いのが実情です。適切な調査設計、実施する際の手順やコスト、実施に伴うリスクなども含め、信頼できる専門家や弁護士の見解を求めることが必要となるでしょう。
この記事の執筆者