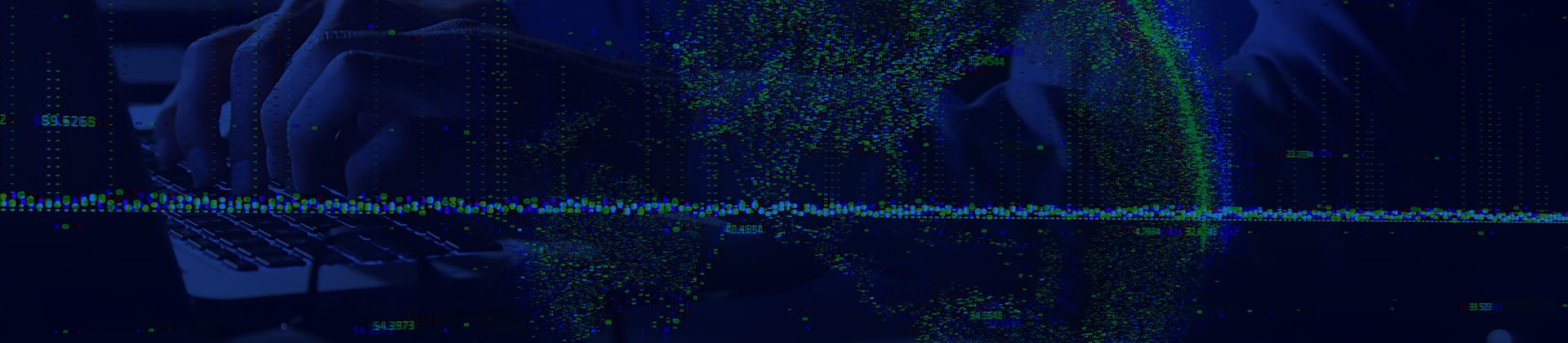官民、業種の枠を越えて、静かに広がる「インテリジェンス」の認識
「経済安保に関する情報発信や意識啓発の促進を目指す国内唯一のカンファレンスと展示会」とうたう、「ECONOSEC JAPAN 2024」の会場を歩いた。そこではさまざまな分野の出展者と登壇者、そして来場者が、官民の壁や業種の枠を越え、ともに国家的な課題である経済安全保障について、互いの知見を惜しみなく共有し、日本の産業界全体の利益を守り、将来の発展に繋げていこうという、新たな「インテリジェンス・コミュニティ」が形成されようとしていた。
2022年5月に成立した経済安全保障推進法(経済活動に関して行われる国家・国民の安全を害する行為を未然に防止するため、基本方針の策定および必要な制度の創設を定めた法律)に基づき創設された4つの制度が、同年8月1日から2024年5月1日にかけて順次、施行された。同法の成立から2年余り経った現在、多くの企業が「経済安全保障」を意識し、自社の事業における必要な取り組みを行ないつつ、模索を続けている。
去る2024年9月12~13日の2日間、経済安全保障に関する情報発信や意識啓発の促進を目指すカンファレンスと展示会「ECONOSEC JAPAN 2024 経済安全保障対策会議・展示会」が開催された。このイベントは、有識者によるエコノセック・ジャパン実行委員会と時事通信社の主催で昨年初めて開かれ、2回目の今年は2日間で延べ1,200~1,300人が来場した。会場で次々と行われた各分野の専門家によるプレゼンテーションやシンポジウム、セッションはどれも満席で、熱心にメモを取る聴講者の姿が目立った。
初日の冒頭は、自民党経済安全保障推進本部・本部長の甘利明衆院議員が基調講演を行い、「経済安全保障は経営リスクとして考えなくてはならない。財務状態が万全の“Sクラス”の会社であっても(経済安保の問題により)、倒産するかも知れない」と切り出した。その現実を示唆する実例として甘利氏は、2021年に日本のエレクトロニクスメーカーが米国国防総省に納入していた700~800億円に上る契約を解除された件を挙げた。このエレクトロニクスメーカーはサイバーセキュリティ基準を満たしていなかったため、国防総省はマルウェアが組み込まれるリスクを回避できないとの理由で契約解除せざるを得なかった。「仮に、この解除された700~800億円が企業の全売上高の大半を占めていれば、倒産の危機に直面する」と甘利氏は指摘した。
「経済安全保障」にはさまざまな切り口がある。出展者は研究機関や法律事務所をはじめ警察庁、公安調査庁、防衛装備庁、コンサルティング・ファーム、サイバーセキュリティ関連、クラウドサービス関連、ブロックチェーン関連、データ解析関連などのIT技術系分野など、官民が集い、それぞれの立場から「経済安全保障」という共通テーマの下で知見の紹介・交換・交流を目指した。
専門家の裾野の広さ
「経済安全保障」を論じる専門家の裾野は広い。登壇者の専門分野も日米関係や米中関係の専門家、サイバー関係、AI関係、法務関係などのほか、大手企業の経済安全保障担当責任者など多彩な顔触れで、登壇者からは「経済安保はコンプライアンスでなくリスクマネジメント」、「企業の各部署にまたがる横断的な業務である」といったコメントが発信され、これにうなずく来場者も少なくなかった。
来場者は、勤務先で「経済安保」の担当になり、何にどう取り組むべきか、その答えを探しにやってきたと思われる若手・中堅社員のほか、自社の事業と業務フローをひととおり経験し、その理解を踏まえて、他社の状況を参照しているような50代以上のシニア社員も多かったように思われる。
セッションに登壇した三菱電機㈱の執行役員で初代・「経済安全保障統括室」室長の伊藤隆氏は、「サイバーセキュリティや産業スパイへの対策など全社を横断して管理している」と自社の取り組みを紹介した。三菱電機では2020年10月に、いち早く社長直轄の「経済安全保障統括室」を設置した。その意義を、「政策動向や法制度を調査・分析し、全社の情報管理・サプライチェーン・産業政策・ESG等に関わる経済安全保障を俯瞰的な視点から統合的に管理」することとしている。その初代室長に就いた伊藤氏は、精力的に外部の講演会などさまざまな場に出かけて、同室の設立経緯や立ち上げから現在までの経過を説明している。
そして、自社が実施している実務上の具体的な対策を披露している。基本的なところでいえば、情報流出のパターンとして1)USB、2)紙=プリントアウトする、3)メール、4)スクリーンショットで写真を撮る――を想定し、このうち、1)はUSBでデータに取り出すことができないようにした、2)は自宅のプリンターなど、会社以外のプリンターでは印刷できないようにした、4)は何枚も写真を撮ることはしないだろうし、画像では見にくいだろうから、優先順位を下げられるため、3)のメールを対策の最優先としたという。その具体策として、例えば、「クラウンジュエル(価値ある技術・ノウハウ)を持つ人と、自己都合での退職が決まった人が退職する日まで、メールをモニタリングしている」という。
テロ対策と危機管理が専門の板橋功・公共政策調査会研究センター長は、今年8月に発覚したNHK国際放送での放送事故[1]と2023年6月に表面化した産業技術総合研究所の技術情報漏洩事件[2]について、「二つの事件はいずれも人的要因である点で共通しており、さらにその当事者がいずれも比較的長く雇用されていた人だった。テロリストでは“スリーパー”と言って(一般社員を装って)10年、20年という長いスパンで勤務し、普通に仕事をこなしている。むしろ、普通以上の仕事ぶりで評価され、信頼を得ているケースが少なくない」と警告した。また、ここ数年多数の日本企業が被害に遭ったサイバー攻撃について、「海外拠点、それも欧米のような主要先進国で攻撃を受けている。海外の全拠点やグループ会社すべてを一斉にというわけにはいかないと思うので、国・地域を特定し、優先順位をつけて取り組んでいけばいい」と、段階的な対策を推奨した。
サイバーセキュリティ分野のソリューションを提供するニュートン・コンサルティング㈱の副島一也社長は、「リスクマネジメントをうまく機能させるためには、最強の経営ツールを活用しなければならない。これができなければ必ず失敗する。では最強の経営ツールとは何か、それは“当事者”を指し、当事者とは経営トップ(社長)。社長が取り組まなければ、リスクマネジメントは機能しない」と話すなど、どの専門家も自身が見聞した企業の実情に照らして、率直な意見を述べた。
このほか、国家の地政学的目的を経済的な側面に焦点を当てて考える「地経学」を研究する国際文化会館地経学研究所(2022年7月に一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブと合併して発足)は、2021年から3年続けて「経済安全保障100社アンケート」を実施している。質問項目は、「米中対立の板挟みになったことはありますか」、「対露制裁の影響」、「台湾有事を想定した対応の状況」などで、例えば、「中国(の企業)と競争していくために何を一番心がけますか」との問いに対して、「研究技術開発(R&D)」が最多で47.9%、次に多かった回答が「知的財産権や特許の管理強化」(39.7%)だったという。
登壇者による興味深い話は続き、2023年1月に「インテリジェンス推進本部」を発足したサントリーホールディングス㈱からは、その本部長を務める江口豪氏(元・北米三菱商事ワシントン事務所長)が、インテリジェンスは各企業が固有の事情に即して取り組んでこそ有効であり、「内製化が必要」としながらも、何もかも単独で行うことは難しいため、部分的に外部に委託しながら進めることも必要と述べた。
[1] 中国籍の契約キャスターが中国語の放送中に、原稿と無関係な発言をし、「釣魚島(尖閣諸島)は中国の領土だ」などと主張した。また英語で、慰安婦問題や南京大虐殺などにも触れて、中国政府の立場に沿って発言した。
[2] 国立研究開発法人「産業技術総合研究所」(茨城県つくば市)の中国籍の主任研究員が2018年4月、研究データを中国企業にメールで送り、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)容疑で逮捕され、東京地検に送検された事件。
共通の利益のために共有する姿勢
先述した甘利氏は、「経済安全保障推進法は常にアップデートしていくべきもので、起こりうる事態を先取りしていく法律である」と述べた。従来、法律とは常に実態の後を追って整備されるもので、実態が先行することはやむを得ないという感覚があった。しかし、経済安全保障では、時々刻々と変化する国際情勢や技術開発の中で、常に先を見てアップデートしていく必要があるという。
そのためにも、例えばサイバーインシデントの官民共有、中国事業での失敗の共有は大きな意味がある、と甘利氏は指摘する。「企業にとっては、サイバーインシデントを政府に報告することはレピュテーションリスクに繋がるうえ、報告のために多大な労力を割かなければならない。だから、報告した企業には的確なアドバイスを返すなど、報告によるメリットを享受できるようにするべきと思う。中国で苦い経験をした企業は多いが、それが公表されたり共有されることはほとんどない。その結果、教訓とならずに同じ失敗が他の企業でも起きている。失敗経験を業界で共有するべき」。
甘利氏が強調した「共有」の意識は、「経済安全保障」という一つの共通テーマを前に、すべてのステークホルダーに芽生えつつある。日本の産業界全体の利益を守るために、ビジネス上はライバル関係にあっても、あるいは官公庁と民間企業という大きな隔たりがあっても、経済安全保障を我がことと認識する新たな「インテリジェンス・コミュニティ」のさざ波が、広い裾野でステークホルダーを交えながら静かに広がっている。
この記事の執筆者