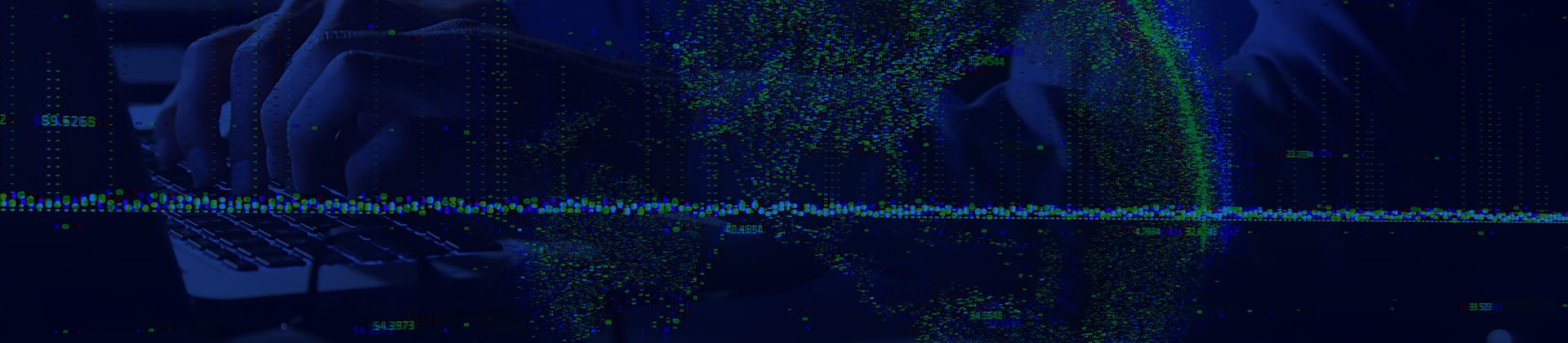はじめに
ビジネスの環境下でも“VUCA(Volatility=変動性、Uncertainty=不確実性、Complexity=複雑性、Ambiguity=曖昧性)時代”と表現されて久しい昨今、世界情勢の変化やAI(人工知能)などテクノロジーの急速な進展、あるいはコロナウイルスの感染拡大などを経て、その認識は日々強まりを見せている。
こうした予測困難な経済環境を生き抜くためには、日々変化する状況に迅速に対応する必要がある。そして、多くのグローバル企業は、革新的な技術や仕組みなどによって新しい価値を生み出し、自ら社会に大きな変化あるいは価値を提供する“イノベーションの創出”に取り組んできた。他方、VUCA[1]という言葉がビジネス界でも用いられ始めた初期の2011年以降、国ごとのイノベーション創出力を評価する指標「Global Innovation Index: GII」での日本の順位は、トップ10圏外となっている。イノベーションの創出において、“無形資産”がいかに重要であるかは言うまでもないが、2020年時点における米国の時価総額に占める無形資産の割合は90%である一方、日本は30%強であるとの分析結果[2]が存在することからも明らかなように、日本企業における無形資産への投資は喫緊の課題といえる。
無形資産によって時価総額を押し上げ、企業価値を最大化しようと考えた場合、財務数値として定量化できない企業の取り組み・活動に関しても、投資意思決定に有用な情報として投資家に提供する必要があり、そのためには、こうした企業活動を定性的にでも可視化することが必要不可欠である。そして、現代企業は、こうしたディスクロージャー機能を『統合報告書』といった任意の情報開示によって果たそうと取り組んでいることを鑑みれば、その“質”が適正な市場価値の獲得において、重要な役割を担っているといえる。
このような考えに基づき本稿では、企業が任意で作成・開示する『統合報告書』を取り上げ、その有効性や機能、重要視すべき視点や押さえておくべきポイントなどを整理するとともに、投資家の意思決定に有効な定性情報の創出を可能とする組織体制などについて検討することで、よりよい統合報告書のあり方について考察したい。
[1] 元々、米国で軍事用語として使われていたものが、2010年以降ビジネス用語として用いられるようになり、2016年の世界経済フォーラム(ダボス会議)で「VUCAワールド」という言葉が使われたことを契機に世界中で認識されるようなったという。
[2] 2022年3月、「非財務情報可視化研究会の検討状況」内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局/経済産業省 掲載産業政策局 (https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sustainability/dai1/siryou4.pdf)
統合報告書の立ち位置
ディスクロージャーとは、企業の情報開示の総称であり、企業がディスクロージャーを行う目的は、一般に投資家が適切な判断を行えるよう、自社の経営実態に関する情報提供を行う点にある。特に資本市場でのディスクロージャーは、「制度上のディスクロージャー」と「任意のディスクロージャー」に大別される。
制度上のディスクロージャーは、金融商品取引法に基づく法定開示制度(有価証券報告書、四半期報告書など)や金融商品取引所における適時開示制度(決算、業績予想、M&A、新規事業、資本異動など重要な会社情報の提供)など、投資家保護の目的から法律・規則によって規制され、開示の内容やタイミングが強制されている。
一方、任意のディスクロージャーは、一般にIR(Investors Relations)といわれ、企業が投資家に対して自社の経営状況や財務情報、非財務情報などを提供し、透明性を高め、投資促進による企業価値向上を目指すような情報開示も含まれる。制度上のディスクロージャーとは異なり、公正な情報提供であれば基本的に規制はなく、企業が方法・内容を決定することができる。本稿で扱う統合報告書も、現状はあくまで企業による任意の取り組みである。
統合報告書の特徴は、“財務情報と非財務情報を統合した報告書”である点といえる。
2013年、国際統合報告評議会(IIRC)[1]は統合報告書の作成に係る指導原則や内容要素をまとめた「国際統合報告フレームワーク(The International〈IR〉Framework)」を公表した(2021年に改訂)。このフレームワークは、原則主義に基づいており、どのように情報を作成・報告するのかを定めた7つの指導原則、何を報告するかを定めた8つの内容要素を設けている。同フレームワークでは、サステナビリティの取り組み、開示を行う上で、マテリアリティ(重要課題)を特定することが求められる。サステナビリティが企業の財務(投資家)に与える課題を「シングル・マテリアリティ」、ステークホルダーの観点から財務のみならず、社会、環境に与える課題を加えたものを「ダブル・マテリアリティ」と呼び、現在においては、世界的にみて「ダブル・マテリアリティ」のほうが主流[2]と考えられる。
日本企業は、世界的に見ても統合報告書に積極的である。2023年に統合報告書を発行した企業等は1017組織であり、その87%に当たる880社が東証プライム市場に上場する企業(92%が上場企業)[3]である。なお、集計期日の2023年12月末時点に東証プライム市場に上場する法人は、1657社[4]であることから、同市場に上場する半数以上の企業が統合報告書を開示していることになる。ちなみに、欧米では、統合報告書はあまり利用されておらず、特に米国では、時価総額上位10社の中で統合報告書を発行している会社はないという。これは、法律や規則で財務情報の開示内容が規定されており、非財務情報は別途開示すればよいため、そもそも「統合」して報告書を作成する必要性が低い[5]ことに由来するが、その背景には、各国における法規則の違いが影響している。欧州ではサステナビリティに関する情報開示が進んでおり、統合報告書の代わりにサステナビリティレポートを発行する企業が多く、米国ではTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に基づく開示が進んでおり、特に気候関連リスクと機会に関する情報が充実しているなどの違いがある。
[1] 2010年に規制者、投資家、企業、基準設定主体、会計専門家及びNGOにより構成される国際的な連合組織として設立された。2021年に、IIRCは、サステナビリティ会計基準審議会(SASB)と合併し、価値報告財団(VRF)が設立された。2022年に、VRFはIFRS財団に統合された。
[2] 現在では、「シングル・マテリアリティ」、「ダブル・マテリアリティ」に加え、時間の経過と環境による変化が企業価値に影響し、財務的にも影響があるという「ダイナミック・マテリアリティ」という考え方もある。これは、主にサステナビリティに関するマテリアリティに用いられ、財務開示にも反映される。
[3] 「日本の企業報告に関する調査2023」KPMG(https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/2024/jp-sustainable-value-corporate-reporting.pdf)
[4] 日本取引所グループ 上場会社数・上場株式数(https://www.jpx.co.jp/listing/co/tvdivq0000004xgb-att/tvdivq0000017jt9.pdf)
[5] 「なぜ、日本では統合報告書が重視されるのか」藤田勉著、『月刊 資本市場』、2023年9月(https://www.camri.or.jp/files/libs/1959/202310021541593702.pdf)
統合報告書の役割と機能
既述の通り、統合報告書には、財務情報と非財務情報を統合する点に特徴がある。財務情報は、有価証券報告書や決算短信といった制度上のディスクロージャーによって、厳格な規律・枠組みの中で開示される。このような制度上の限界を超えて、企業の価値創造能力に資する無形資産を定性的にとらえ、財務情報との連関を意識しながら各ステークホルダーに対して説明しようとする試みが統合報告書を映す一側面といえよう。こうした取り組みを会計的側面からとらえれば、非財務情報が財務情報の補完的役割を果たす[1]との認識あるいは、あくまで“任意”のディスクロージャーであるという現状から、統合報告書に財務報告の補完機能が期待できるという文脈で語られるかもしれない。しかし、欧米と異なり、多くの日本企業が、財務情報と非財務情報をあえて“統合”することに意味を見出したと(あるいは、結果として多くの企業が統合報告書の発行を選んだ現状を)考えれば、制度上のディスクロージャー以上に統合報告書が投資判断の材料として活用される未来も期待できるのではないだろうか。
将来予測の困難な現代において、上場企業は常に“イノベーション創出”のプレッシャーにさらされている状況にある。企業は、目まぐるしく変化するビジネス環境や情勢に対応すべく、日々の情報収集ならびに業務に取り組んでいる。このような現況は、過去に意思決定した結果としての財務報告にとどまらず、定量化できない企業の取り組み・活動を定性的にとらえ、自主的に開示する統合報告書の機能がますます重要になることを示唆しているといえよう。そして、こうした統合報告書の役割あるいは、財務情報と非財務情報が連関する特性に着目すれば、企業の短、中、長期の価値創造能力に影響を及ぼす経営・事業戦略上の具体的な課題や直面する可能性が高い不確実性などについて、これまで以上に国内外の関連情報の収集、整理、分析を行ったうえで、中長期の価値創造プロセスのストーリーにつなげていくことが求められるだろう。
このようにVUCA時代における企業やステークホルダーに影響を与え得るリスクと機会、不確実性をより的確に捉え、会社としての在り方・経営者の考え、あるいはパーパスから導き出されたパフォーマンス・ドライバー(事前の行動指針)を起点に取り組んだ活動が結果としての財務情報に結実するプロセスを的確に表現することが、報告の質を高め、信用に足る情報を投資家やその他のステークホルダーに提供することにつながる。
つまり、統合報告書で最も重要な点は、「財務情報と非財務情報をストーリーとして結合すること」、「活動と資本の関係がストーリーをもって結合すること」[2]であり、投資家等の情報利用者は、これによって企業の一連の事業活動を、「原因」と「過程」と「結果」をもって理解することができるのである。
統合報告書では、マテリアリティ分析を通じて、企業が優先的に取り組むべき重要な課題を明らかにし、投資家をはじめとするステークホルダーに対してその取り組みを明確に伝える。マテリアリティは、一般に「重要課題」と訳され、企業の持続可能性や社会的責任を果たすための多岐にわたる課題の中から、特に優先して取り組むべき重要課題が特定される。このため、統合報告書によって提示される企業の価値創造能力は、ESGやSDGsに対する取り組み・活動にフォーカスされることが多い。
マテリアリティ特定の出発点は、会社の在り方・経営者の考え、パーパスであり、これを前提とした将来の経済環境の見通しや、その見通しの中で想定しうる“リスクと機会”ならびに、それが企業行動に及ぼす影響を示すことが投資家の意思決定に有用な情報であるために必要不可欠である。つまり、統合報告書は、“リスクマネジメント”の基礎の上に成り立っていると認識する必要があり、その過程で得られた様々なリスク情報(機会を含む)に対して、経営トップが価値創造に向けた舵取りを戦略的に示すこと、経営トップの意思決定が適切に機能しているかを組織的に把握・監視できている状態にあること――を的確に示すことが、統合報告書の有効性と信頼性の向上において重要な要素になると考える。もちろん、いくら任意のディスクロージャーであるとはいえ、主な情報利用者が国内外の投資家であることを念頭に置けば、統合報告書の信頼性確保のため、国際基準やフレームワークを参考にしながら、「比較可能性や完全性」の観点についても十分に配慮した、明瞭で透明性の高い内容にすることが望ましい。
[1]『統合報告革命 ベスト・プラクティス企業の事例分析』古賀智敏責任編集、池田公司編集、税務経理協会、2015年。本著において、「実験研究の結果、企業評価並びに投資決定目的に対して、財務情報が情報利用者の主たる情報なし、人的資本情報など非財務情報は従的役割を持つにすぎないことが実証された」とある。
[2] 『価値共創のための統合報告~情報開示から情報利用へ』、伊藤和憲著、同文舘出版、2021年。
統合報告書の“質”向上と社内インテリジェンス機能
投資家やその他のステークホルダーにとって有用な統合報告書には、「財務情報と非財務情報」や「活動と資本の関係」がストーリーをもって結合することが重要であり、この点の実効性を確保するためには、リスクマネジメントに基づく様々な情報の収集・整理・分析という社内インテリジェンス機能が必要不可欠である。「結果」としての財務情報やそれを補完あるいは、「原因」や「過程」との因果関係を明らかにする非財務情報は、それに至るプロセスにおいて、創出・選定・整理され、様々な戦略的思考・高度な経営判断(重要度や機密性の評価を含む)を経て、報告すべき情報以外はそぎ落とされた上で、統合報告書内に収束する。そのためのインプット情報は膨大かつ多岐にわたり、担当部署も様々である。
ただ、とかくリスクにかかわる情報については、タイミングや精度の違いはあれど、法務・コンプライアンス(あるいは、危機管理)部門に集まることが多い。リスクと機会は表裏一体であり、事業戦略の実行にはリスクがつきものであるため、経営意思決定機関と法務・コンプライアンス部門は緊密に連携する必要があり、また、経営者の考え自体がマテリアリティ特定の出発点であることを鑑みれば、同部門が社内におけるインテリジェンス機能の一翼を担う必要があることは明白といえよう。加えて、コーポレートガバナンスの観点でも、当該部署が組織内で果たす機能や社外取締役・監査役との関係性、距離感という意味でも、統合報告書の信頼性に寄与することができるものと考える。
ただ、法務・コンプライアンス部門が社内インテリジェンス機能を果たすうえで注意しなければいけない点もある。それは、実務上同部門が、ビジネスの“ブレーキ”になっている、あるいは、社内でそう認識されているケースが少なくない点である。現場部門から契約締結やサービスローンチの直前になって案件が持ち込まれたとして、その案件に受容できない致命的なリスクが存在していれば、同部門は急ブレーキを踏んで案件を止めるしかない。しかし、その結果、現場部署からは「案件をつぶされた」等の評価を受け、それが社内に浸透するようなことになれば、法務・コンプライアンス部門にリスクと機会にかかわる情報が、網羅的あるいはタイムリーに集まらなくなるのは、想像に難くない。これでは、質の高い統合報告書の創造に寄与するインテリジェンス機能を果たすどころか、本来のリスクマネジメント機能すら十分には果たすことはできない。
ここで重要になるのが、法務・コンプライアンス部門の役割が“ブレーキ”ではなく、ビジネスの行先に待ち受ける将来リスクに対して、前もって備えることのできる“ヘッドライト”である[1]との意識改革である。この意識で普段から現場部門との信頼関係を構築し、維持向上することができれば、日常的に、リスクと機会にかかわる情報が法務・コンプライアンス部門に集まる情報集約の道筋が生まれ、同部門に期待される社内インテリジェンス機能の実現に近づくことができるだろう。さらに、法務・コンプライアンス部門がヘッドライトとして機能すれば、現場部門がアグレッシブにリスクを取りに行くことができる。つまり、リスク管理にとどまらず、機会の創出に対しても法務・コンプライアンス部門が前向きに貢献する形になるのである。
[1] 『図解 不祥事の予防・発見・対応がわかる本』竹内朗編、プロアクト法律事務所著、中央経済社、2019年。
「量」から「質」へ ―― 統合報告書をアップグレードする「社内インテリジェンス」
本稿は、予測困難なVUCA時代において、中長期的な企業価値を生み出す力としての無形資産と、それを非財務情報として可視化し、投資家に有用な情報として提供する試みとしての統合報告書に関する考察を行うことで、当該報告書の質向上に資する社内インテリジェンス機能の在り方に接近しようとしたものである。
これまで統合報告書における非財務情報は、ESGやSDGsを企業活動として如何にとらえるかという視点で語られることが多かったが、不確実性が高く、将来予測が困難な現在の経済環境下で企業価値向上に取り組む前提に立てば、目まぐるしく変化する世界情勢(経済安保やセキュリティクリアランス)や成長に向けた具体的な事業戦略(M&A等)などについて、意識的に取り上げ、財務情報との結びつきなどをストーリーとして説明することが、投資対象としての企業価値や信頼性を適切に評価することに貢献するとの結論に違和感はない。そして、こうした効果を統合報告書に期待する場合、会計部門とともに収録情報の収集・整理・分析の一翼を担う法務・コンプライアンス部門がインテリジェンス機能を果たすことが、実効性を高めるうえで重要である。しかしながら、多岐にわたる情報の収集・分析には、相当の専門性と時間・労力を有する一方、多くの企業では、当該部門のリソースがそれに耐えるに十分でないという課題がある。その意味では、これを支援・補強する機能を外部に求めることも一案といえる。
最後に、日本企業は統合報告書に積極的な一方、一部の調査報告では、その“質”について、国際的にみて下位に属するとの指摘[1]もある。このため、本稿で提示した「財務情報と非財務情報をストーリーとして結合すること」、「活動と資本の関係がストーリーをもって結合すること」という視点と当該報告書を創出するための社内インテリジェンス機能に着目しながら、日本企業が開示する統合報告書の分析を進めることは、統合報告書の質向上ひいては、中長期的な企業価値向上に寄与する可能性があるといえよう。 当社では、統合報告書の質を高めるための第三者視点による分析や、法務・コンプライアンス部門のインテリジェンス機能支援も行っております。
[1] A Comparative Analysis of Integrated Reporting in Ten Countries, Robert G. Eccles, Michael P. Krzus, and Carlos Solano, 2019.
この記事の執筆者