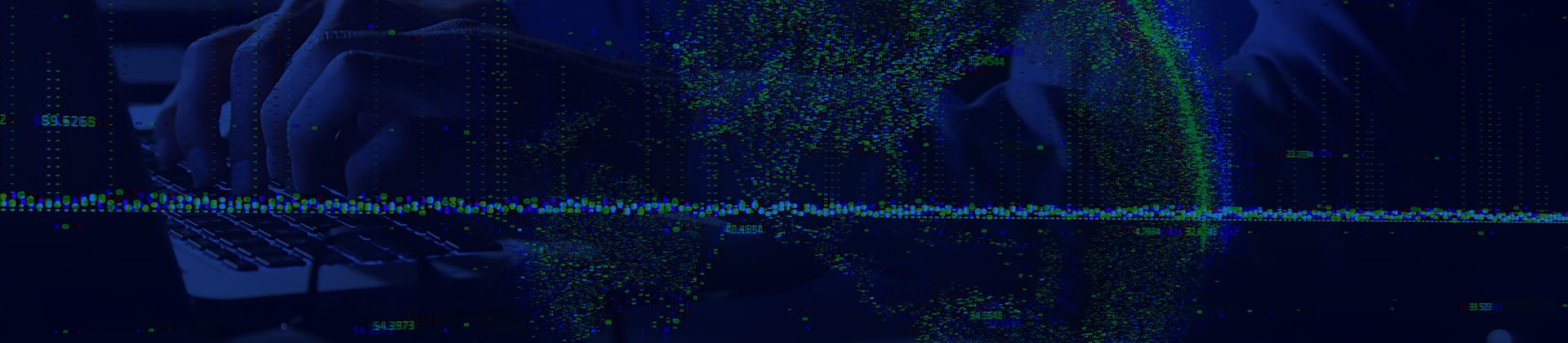はじめに
当社は、日系インテリジェンス・カンパニーとして、クライアント企業のみなさまに対し、その経営判断などに資する「精査された情報(インテリジェンス)」を提供するために、日々、さまざまな情報収集・分析を行っております。
ところでそもそも「インテリジェンス(intelligence)」とは何なのでしょうか。インテリジェンスとは、論者の数だけ定義もあるといわれるほど、さまざまな意味合いで理解されている言葉ですが、今回は、「小説に学ぶインテリジェンス」という切り口で、英国の作家ジョン・ル・カレ/John le Carré(1931- 2020)と彼の作品を通じて、その示唆するインテリジェンスのあり方について考えてみたいと思います。
複雑な幼少期を経て学生諜報員に
いわゆるスパイ小説の巨匠として知られる ル・カレですが、彼自身、冷戦期の1950年代末から60年代前半にかけて、英国のMI5(保安局)[1]およびMI6(秘密情報部/SISとも呼ばれます)[2]に勤務した経験を持ちます。インテリジェンス・オフィサーとして情報を扱うプロだったル・カレの経験は、彼の作品の随所に活かされています。

Image: Krimidoedel
ル・カレの生い立ちはやや複雑です。ル・カレ(本名はデイヴィッド・ジョン・ムーア・コーンウェル/David John Moore Cornwell)は1931年10月、英国南部のドーセット州プールで生まれました。父親のロニーは詐欺師であり、ル・カレが2歳のときに詐欺罪で服役しています。母親のオリーヴは夫の破産と不倫に耐えかねて、ル・カレが5歳のときに交際相手と駆け落ちし、家族のもとを去りました。少年時代のル・カレは父親が繰り返し友人や親戚に金を無心する姿を目の当たりにしたといいます。
ル・カレは、名門パブリックスクールのシャーボーン校に入学しましたが、厳格な校則を嫌って16歳で中退し、スイスのベルン大学でドイツ語やドイツ文学を学びます。その後、英国に戻り、1952年10月にオックスフォード大学へ進みました。オックスフォード在学中はMI5の依頼で学内の左派組織に加わり、要注意人物の監視などを行っていたといいます。当時、英国では著名な外交官2名がソ連のスパイだったと発覚し、大きなスキャンダルになったこともあり、MI5は英国全域の左派組織への潜入調査に躍起になっていたとされます。
[1] 諜報活動や破壊活動から国家を守り、国内の治安維持を担当する情報機関。ル・カレが勤務していた当時は英領植民地も活動範囲に含まれていたといいます。
[2] 秘密情報の収集と海外での秘密行動を担う組織で、英政府は1990年代前半までその存在を公式に認めていませんでした。MI5とよく対比されるMI6ですが、MI5を「守りの組織」とすれば、MI6は「攻めの組織」と言うことができるかもしれません。
MI5での日々:不十分な粘土の塊をこねまわして、人の姿を作る
ル・カレは現代言語学の学位を得てオックスフォードを卒業すると、パブリックスクールのイートン校での教職を経て、1958年の春、26歳のときにMI5に正式に採用されました。MI5では、思想上、要注意人物とされる公務員や科学者らの「身元調査」を行う部門に配属されます。調査対象となる人物の現在の同僚や以前の仕事仲間、雇い主、恩師などしかるべき関係者から信頼できる情報を引き出し、その他のさまざまな手段で得られた情報とすり合わせて精査することが彼の日常業務となりました。ル・カレは「水槽のような狭い部屋」で朝から晩まで、手元に集まってくる生情報を元に、会ったことも見たこともない人物に関する「インテリジェンス」を作り出す日々を送りました。
彼は後年、MI5での業務を次のように振り返っています。「私はたんに、電話の盗聴記録や盗み見た郵便物、調査員の報告といった不十分な粘土の塊をこねまわして、人の姿を作った。対象者について欠けている情報は想像で補った」[1]。この一節は、ル・カレによるインテリジェンスのみごとな定義といえます。
[1] アダム・シズマン『ジョン・ル・カレ伝 上』(早川書房、2018年)
「インテリジェンス小説」としてのル・カレ作品
ル・カレが作家としての活動を本格的に始めたのは、1960年6月、ル・カレがMI5からMI6に移籍した頃とされています。第1作『死者にかかってきた電話』が出版されたのは、1961年に彼が西ドイツ(当時)・ボンの英国大使館に赴任した直後のことでした。外務省の職員が本名で出版することは禁じられていたため、書き手が英国人と分からないよう、「ジョン・ル・カレ」というアングロ・サクソン風ではない筆名を使ったといいます。
ル・カレがボンに赴任した年の8月13日、東ドイツ(当時)によって突如ベルリンの壁の建設が始まります。東西ベルリン分断の様子を現地で目の当たりにしたル・カレが1963年に著したのが、英国と東ドイツとの諜報戦を描いた『寒い国から帰ってきたスパイ(The Spy Who Came in from the Cold)』です。ル・カレにとって3作目となるこの作品は世界的ベストセラーとなり、数々の賞も受賞したことで、作家ジョン・ル・カレの名は広く世に知られるようになります。
ル・カレの作風は、たとえば、イアン・フレミング(Ian Fleming)が描いた「007」シリーズのような派手なアクションや大胆なロマンス、あるいは便利なガジェットとは無縁です。敵味方や善悪の境もはっきりしない、冷徹で無慈悲な諜報の世界に身を置くル・カレの作品の主人公の多くは、ル・カレ自身がかつてそうだったように、生情報である「インフォメーション」を地道に集め、その断片をジグソーパズルのように組み合わせることで、政府の意思決定に資する「インテリジェンス」を生成することをミッションとします。
地味で泥臭い作業をコツコツ進める姿は、古今東西を問わず「インテリジェンス」の現場の実像に近いものといえます。その意味で、ル・カレの一連の作品については、「スパイ小説」というよりはむしろ「インテリジェンス小説」と呼ぶほうがふさわしいかもしれません。
地味な、あまりにも地味な情報収集と分析を描く
ル・カレの最高傑作のひとつとされるのが、1974年に発表された『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ(Tinker Tailor Soldier Spy)』です。舞台は冷戦下、ソ連との激しい諜報戦を展開していたMI6を思わせる英国の情報機関で、通称は「サーカス」。このサーカスを不本意な形で追われた元諜報員のジョージ・スマイリーに、ある日、古巣に潜むソ連の二重スパイ「もぐら」を突き止めるよう英政府高官から極秘任務が下されます。スマイリーはずんぐり小太りの外見で、妻に去られ、やや人生に疲れた初老の英国紳士として描かれています。ジェームズ・ボンドのような華麗なダンディズムとは対極にある描写です。
このスマイリーですが、組織を去った身であることから、サーカスに出入りすることはできません。そこで彼は、ごくわずかな信頼できる仲間を通じて、サーカスの職員録や職掌要覧、当直日誌、経費の精算書類、ソ連大使館員の出入国記録といったさまざまな資料を集めることから始めます。それらに記載された膨大な情報を整理して丹念に読み解きながら、役に立ちそうな情報の断片を拾い集め、自らの記憶と経験も駆使して、「もぐら」の正体を突き止めようとしていきます。
ところで、上記のとおり、本作の舞台となった「サーカス」はル・カレが勤務したMI6がモデルとされます。ただし本作の執筆当時、MI6本部はル・カレが勤務していた場所から移転していたので、ル・カレは新しいMI6本部の様子を描くために、移転先の建物(これを彼は「ある地味な建物」と表現しています)の外観を参考に、建物内の間取りを推測し、細部まで想像しながら執筆したといいます。目立たない入り口、薄暗い廊下、ほこりだらけの書類ロッカー、おしゃべりな守衛といったサーカスの舞台背景の描写は、ル・カレが駆使した「インテリジェンス」の賜物というべきでしょう。
こうしたル・カレの作風は、かつて要注意人物の「身元調査」を行っていた当時の経験を存分に活用して形作られたといえますが、断片的な情報から有用なインテリジェンスを作り上げていくという意味では、たとえば当社の行うOSINT(公開情報の収集・分析)の業務とも軌を一とします。
ル・カレの作品には、諜報員というよりはインテリジェンス・オフィサー(情報分析官)と呼ぶべき人物が数多く登場します。その一人が、『ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ』の作中、サーカスでの“調査の女王”と称されるコニー・サックスです。サーカスで辣腕をふるった分析官である彼女はいち早く、「もぐら」の気配を察知し、その正体を突き止めようとします。ル・カレは、コニーがサーカスに在職中、ソ連のスパイを見つけ出そうと、ソ連陸軍の任官公報に偽装の記載がないかを確認するため、英陸軍のモスクワ・ウォッチャーたちとしらみつぶしに公開情報に当たり、情報分析を進め、やがて最終的な“容疑者”を数人にまで絞りこんだというエピソードが挿入されています。
調査への情熱と一風変わった思い込みの激しさを併せ持つ女性として描かれるコニー・サックスには実在のモデルが存在し、それはル・カレによると、第二次世界大戦中にブレッチリー・パーク(Bletchley Park)[1]でナチスドイツの暗号解読に当たった英国人女性チームのメンバー、ダイアナ・マンフォード(Diana Mumford)だとされます。
[1] 英国・バッキンガムシャーにある邸宅を指しますが、第2次世界大戦中には政府の暗号学校が置かれていたことから、その学校の通称として用いられることもあります。この学校は、英国の数学者・暗号研究者として著名なアラン・チューリングが勤務したことでも知られています。
自叙伝を書くために調査員を雇い、自らを調査する
ル・カレの作品の多くは東西冷戦を題材としていますが、冷戦が終結した後も、ル・カレは筆を振るい続けました。『ナイロビの蜂(The Constant Gardener)』(2001年)では多国籍企業によるアフリカ収奪の構造を背景に、妻の死の真相を追う英外交官の姿を、『スパイはいまも謀略の地に(Agent Running in the Field)』(2019年)では、欧州連合(EU)離脱と対ロシア政策に頭を悩ませる英国の「窓際」諜報員を描きました。
ところでル・カレには、晩年、自叙伝の執筆の話が持ち上がったものの、自らの生い立ちや経歴に関連する情報があまりにも少ないことに頭を悩ませたといいます。そこで彼は民間の調査員を2人雇い、「遠慮なくあちこちを訪ねて、生きた証人と書面の記録を見つけ、私と家族と父に関する事実を集めてきてほしい」と依頼したとされます。ル・カレはその調査員たちに、父・ロニーが関係した裁判記録を調べることを勧め、またロニーの元秘書、看守、警官などの「人的情報源」を追うよう指示しました。併せて、ル・カレ自身の学校や軍隊での記録も調査するよう伝えて、こう釘を刺しました。「くれぐれも私に気兼ねして中途半端な調査はしないように」と。このエピソードからは、事実を重んじた元情報部員あるいはインテリジェンス小説の書き手としての矜持が垣間見えます。
ル・カレの「想像力」を、現代のビジネス・インテリジェンスへ
このように、ル・カレの作品の随所で描かれるインテリジェンス・オフィサーの仕事ぶりを振り返ると、それが当社を含む民間インテリジェンス・ファームの業務内容ときわめて近似していることに気づかされます。
もともと「インテリジェンス」という営為は、国家安全保障の領域の専売特許として理解されてきたように思われます。しかし、「インテリジェンス」を扱う主体が国家であろうと民間であろうと、その基本的なプロセスには共通する部分が少なくありません。いうまでもなく民間インテリジェンスの世界では、国家インテリジェンスの世界に往々にしてみられる超法規的な手法とは無縁です。公開情報の収集分析や人的情報源からの聞き取り調査など、その気になれば誰でもアクセス可能な情報源から得られた複数の情報を丹念に整理し、分析し、そしてクライアントの意思決定に資する「インテリジェンス」へと再構築する。これが民間インテリジェンスの手掛ける作業の大枠です。そしてこうした作業はル・カレの作品に描かれているように、その地道な作業や多面的な分析と想像力の駆使などの点において、国家インテリジェンスとも多分に重なる面があります。
民間インテリジェンスが公開情報のみを用いているといっても、その作業から得られる成果は、想像以上に精緻で立体的で説得力に富むものとなりえます。上質なインテリジェンスを生み出す最後のカギは、「現実にうなずかれるような想像力(imagination that owed only a nod to the reality)」(ル・カレ本人の言葉)かもしれません。
私たちJPR&Cは、その「想像力」と「分析力」を駆使し、クライアントの皆様の不確実な未来を照らす一助となりたいと考えています。
この記事の執筆者