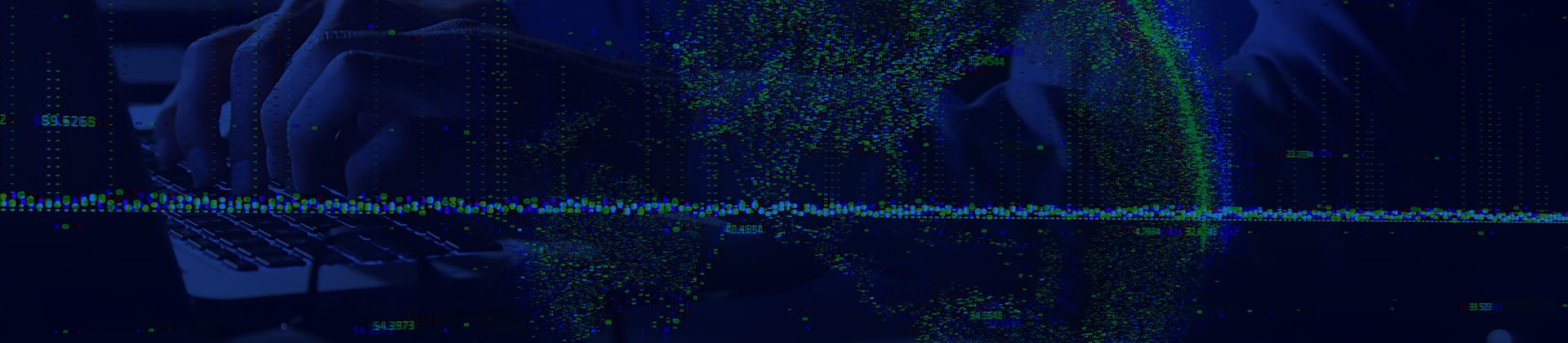本稿では、財務情報だけでは見えないリスクを洗い出す『リスク・デューデリジェンス®』の手法とその重要性について解説します
現代企業が直面する「見えないリスク」
当社が提供している「リスク・デューデリジェンス®」は、デューデリジェンスのなかでも、財務デューデリジェンスなどでは把握しづらい「非財務リスク」「定性的なリスク」を洗い出し、取引相手の健全性・適格性の評価、あるいは取引相手の総合的な「企業価値」の判断に資するための情報収集・分析のアプローチを意味します。ここでいう「リスク」とは、取引相手の反社会的勢力との関係性や役員・大株主の逮捕歴・処分歴等の不芳情報はもちろんのこと、対象企業のコンプライアンスやガバナンス、国内外子会社・関連会社不正等の内部統制上のリスク、またESGにおける物理的リスクや移行リスク、さらに、特に海外企業が対象の場合は、上記に加えて、マネーロンダリング・テロ資金供与(AMT/CFT)、贈収賄・腐敗リスク、サプライチェーンや人権リスク、地政学・経済安全保障に絡むリスクなど、きわめて多岐にわたります。
そうした多面的な観点から収集された情報を整理・分析することにより、取引相手の健全性・適格性の評価、および「企業価値」をめぐる総合的評価に資することが「リスク・デューデリジェンス®」の主たる狙いとなります。
「不自然さ」を見抜く調査プロセス
ここでは、人的資本に絡む「リスク・デューデリジェンス®」の具体的な調査プロセスの一端をご紹介します。
まず対象となる企業には、長短はともかく「歴史」がありますので、創業から現在に至るまで、どのような変遷を辿ったのか、その時々の企業の意思決定にどのような背景があったかなどを把握するために、公開情報を丹念に取集することで、どの情報が開示され、逆にどの情報が開示されていないかなどをチェックし、“不自然さ”の有無を見極めることが一つの着眼点となります。経営陣の顔ぶれの変遷なども見るべきポイントです。たとえば、創業以来、同族で運営してきた企業に、突然非同族の人物が役員に就任し、創業一族が全員退任する事実が認められた場合には、その「非連続性」をめぐる理由・背景(乗っ取りの可能性など)を見極めることが求められます。
さらに事業内容の変遷も重要なポイントといえます。創業以来10年以上トラック運送業のみを行っていた会社が、突然アパレルショップの運営を開始するなど、会社の主業とは業種的に関連性を見出せない事業目的が追加された場合、その「不自然さ」に着目してその理由・背景を探ることが必要となります。
このように公開情報で得た情報から“不自然さ”を感じた部分について、より深堀すべきポイントを整理した上で、人的情報収集、現地調査、あるいは必要に応じて行動調査なども導入し、これら複数のアプローチで収集された情報を突合させ、そこに相違点や不自然な点があれば、再度、公開情報を確認し、必要であれば、現地調査やヒアリング調査も追加で実施するなどして、“情報の精度”を高めていきます。
こうしたプロセスを通じて得られた個々の断片的な情報を総合的に整理・分析し、“使える情報”へと仕立てていくことにより、その会社の「人的資本」をめぐる「インテリジェンス」が生成されることとなります。
企業価値評価との関係(IIRCの非財務資本)
「リスク・デューデリジェンス®」の具体的アプローチはクライアントである企業のご要望に応じて、千差万別になりますが、以下では一例として、いわゆる「企業価値」の評価をめぐる「リスク・デューデリジェンス®」の観点をご紹介したいと思います。
企業価値とは、一般的に「企業全体の経済的価値」を指し、主な算定手法として、企業が将来に生み出すキャッシュフローを現在価値に割り戻す「割引キャッシュフローモデル」が多用されますが、投資家(株主)が投資の意思決定を行うに際して、この企業価値の算定に財務情報に加えて非財務情報も反映する必要があり、この投資家(株主)の意思決定に有用な情報、さらにその他の幅広いステークホルダーとも共有する情報の観点から、企業には統合報告書において、財務情報に加え、非財務情報の開示が求められているところです。
2010年に英国で設立された「国際統合報告評議会(IIRC)」[1]は『国際統合フレームワーク』において、非財務資本を、下表の通り、製造資本、知的資本、人的資本、社会・関係資本、自然資本に整理しています。
【IIRCが示す非財務資本の内容】
- 上表は『国際統合フレームワーク』(日本語版)[2]の内容をもとに当社調査部が作成。
| 非財務資本 | 概要 |
| 製造資本 | 製品の生産又はサービス提供にあたって組織が利用できる製造物(自然物とは区別される)。 たとえば、建物、設備、インフラ(道路、港湾、橋梁、廃棄物及び水処理工場など)など。なお、製造資本は一般に他の組織によって創造されるが、企業が販売目的で製造する場合や自ら使用するために保有する資産も含む。 |
| 知的資本 | 組織的な、知識ベースの無形資産。 たとえば、特許、著作権、ソフトウェア、権利及びライセンスなどの知的財産権、暗黙知、システム、手順及びプロトコルなどの「組織資本」など。 |
| 人的資本 | 人々の能力、経験及びイノベーションへの意欲。 たとえば、組織ガバナンス・フレームワーク、リスク管理アプローチ及び倫理的価値への同調と支持、組織の戦略を理解し、開発し、実践する能力、プロセス、商品及びサービスを改善するために必要なロイヤリティ及び意欲であり、先導し、管理し、協調するための能力など。 |
| 社会・関係資本 | 個々のコミュニティ、ステークホルダー・グループ、その他のネットワーク間又はそれら内部の機関や関係、及び個別的・集合的幸福を高めるために情報を共有する能力。 たとえば、共有された規範、共通の価値や行動、主要なステークホルダーとの関係性、及び組織が外部のステークホルダーとともに構築し、保持に努める信頼及び対話の意思、組織が構築したブランド及び評判に関連する無形資産、組織が事業を営むことについての社会的許諾(ソーシャル・ライセンス)など。 |
| 自然資本 | 組織の過去、現在、将来の成功の基礎となる物・サービスを提供する全ての再生可能及び再生不可能な環境資源及びプロセス。 たとえば、空気、水、土地、鉱物及び森林、生物多様性、生態系の健全性など。 |
これらの個々の非財務資本について、価値の創造と保全、毀損の理論的な裏付けの一部として、リスクと機会の観点から考慮していくことが、企業の本質的な価値を探るうえで重要となります。
企業はこれらの非財務資本を考慮し、短・中・長期の価値創造に影響を及ぼす具体的なリスクと機会を特定し、それらに対し、どのような取組みを行っているかについて、統合報告書で開示することが求められます。リスクについては、影響度と発生可能性の観点から重大なリスクをマテリアリティとし、当該リスクに対する組織のアプローチを統合報告書に盛り込みますが、「リスク・デューデリジェンス®」はまさにこのマテリアリティを含むリスクの内的・外的要因を特定・評価するとともに、そのリスクを低減、管理し、機会からの価値を極大化していくための企業の重要なアプローチの一つと言えるでしょう。各非財務資本を考慮したリスク・デューデリジェンス®の例として、たとえば、「知的資本」については、特許や著作権などの申請・取得状況あるいはその侵害事案の有無などが対象となり、また「人的資本」については、経営陣の能力、経験などに加えて、組織ガバナンスの実態、コンプライアンスや法令遵守の状況などが対象となります。また、「社会・関係資本」については、株主構成、主要なステークホルダーとの関係性、社会的貢献への意識、ブランド的価値、レピュテーションの実態などが対象となります。
さらに地政学的状況や環境などの外部要因によっては、製造資本、自然資本に加え、財務資本の低減・毀損にもつながりかねず、リスク・デューデリジェンス®を通じて各種リスクの特定・評価を行っていくことが肝要です。
「リスク・デューデリジェンス®」は、企業の非財務資本をめぐるリスクと機会に着目することにより、企業の総合的な価値評価に資するインテリジェンスを提供するものといえます。
[1] 規制当局や、投資家、標準設置機関、会計機関、学術団体のほか、世界23か国の有力企業約90社が参加している。
[2] https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/International_IR_Framework_JP.pdf
コラム:デューデリジェンス小史
「リスク・デューデリジェンス®」は、「リスク」と「デューデリジェンス」が組み合わさった言葉ですが、
デューデリジェンスとは、文字通り「しかるべき(due)努力(diligence)」を意味します。古代から今日に至るまで、その本質的な意味は変わりません。古くは、『旧約聖書』にその萌芽が見られ、その「エズラ記」第6章12節末尾に「私、ダリヨスは命令を下す。まちがいなくこれを守れ」との一節がありますが、英語訳[1]では「I, Darius, have issued this decree; let it be carried out quickly and with due diligence.」との表現が用いられています。
また英語表現としての「デューデリジェンス(Due Diligence)」のもっとも初期の用例は、シェイクスピアと同時代、英国の政治家で文人であったRichard Carew(1555-1620)が著した詩『ニシンの話(A Herring’s Tale)』(1598年)に登場する一節、「国王らは、その命令をしかるべき努力で従わせしめた(Monarchs had their commands obeyed with due diligence.)」とされています。この段階でも、この言葉は、依然、素朴に「しかるべき努力」を意味していましたが、その後、18世紀あたりから、たとえば欧州の国際法における用語として、「国家が自国領域内の外国人を保護するために求められる相当の注意(due diligence)」[2]などといったかたちで、より具体的な意味を帯びるようになりました。

デューデリジェンスが、より今日的な意味内容を持つに至った契機として、米国の「1933年証券法」(第11章)が知られています[3]。同法では、証券公募にあたり、証券取引委員会(SEC)に提出した登録届出書に重要な事実の不実記載などがあり、その結果、その証券を取得した人物に損害が及んだ場合、その人物は、証券発行者等に損害賠償請求ができるとしたものです。ただし同法は、その発行者が「合理的な調査」を行い、登録届出書に重要な事実の不実記載がないことを信じる合理的理由があり、実際にそう信じたことを証明できれば免責になる、と定めています。
「合理的な調査」を通じて「重要な事実の不実記載がないこと」を明らかにすることが、証券発行者に求められる「しかるべき努力(デューデリジェンス)」というわけです。米国法学界では、同法の免責条件に基づく免責の申し立てについて、その後、「Due Diligence Defense」と呼ぶことが通例となっています。
今日のデューデリジェンスの射程
この「1933年証券法」(第11章)は「デューデリジェンス」と「調査」が初めて明確に結びつけられたという意味で注目できます。ここから今日のデューデリジェンスは、M&Aなどの投資行動や不動産購入等の重要な商取引において、対象となる企業や不動産等の価値、将来の収益性、潜在的リスクなどについて調査を通じて把握することを意味するようになりました。重要取引に先立ち、「筋の悪い取引」、「関係者に損害を及ぼし得る取引」を未然に回避するために当事者に求められる「しかるべき努力」としての調査、これが今日、ビジネス用語として用いられるデューデリジェンスの意味です。
[1] 原語のニュアンスを再現している英訳版として名高い以下のバージョンを参照しています。Amplified Holy Bible, Captures the Full Meaning Behind the Original Greek and Hebrew, Zondervan, 2015.
[2] 我が国の国際法の世界では、due diligenceには「相応の注意」との日本語訳があてられることが一般的とされます。なお、本稿では立ち入りませんが、近年、国際法学では、「Due Diligenceのルネサンス」が語られるなど、この概念が改めて注目されるようになりました。
Cf. Samantha Besson (2023), Due Diligence in International Law, Brill.
[3] 同章には「due diligence」という語そのものは登場しませんが、今日、ビジネス用語として用いられるデューデリジェンスに近似する意味内容を初めて明示した一節として知られています。
この記事の執筆者