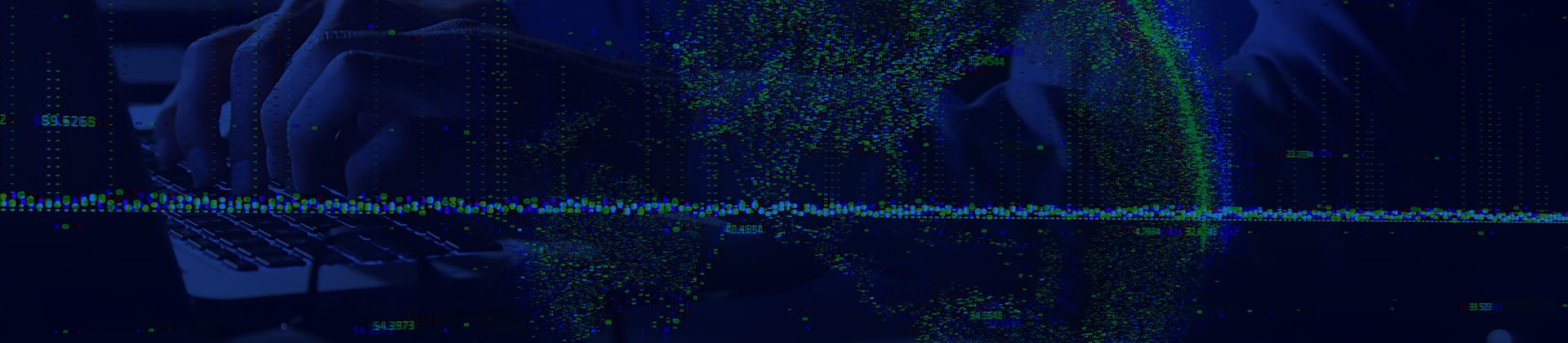——— 我々の一人が、地球上の人間がかつてないほどたがいに接近していることを証明するために、次の実験を行うことを提案した。まず地球上の 15 億人の住民の中から、どこの誰でもいいから1人選ぶがいい。彼は言った。賭けてもいいが、自分の個人的な知人から始まり、その知人、その知人、と5 人以内のつながりで、きっとその選んだ1人に到達できるさ、と。
カリンティ・フリジュシュ『連鎖』より
はじめに
上の引用は、ハンガリーの作家カリンティ・フリジェシュ(Karinthy Frigyes)が1929年に発表した『連鎖(Láncszemek)』という小説の一節[1]です。この一節は、のちに「6次の隔たり(Six Degrees of Separation)」と呼ばれることになる、今日のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の理論的下地とされる見解をもっとも初期に表明した事例として知られています[2]。
「6次の隔たり」とは、端的に、地球上の誰とでも5人を介せば繋がれるという理論ですが、裏を返せば、個人の知人・友人のネットワークは、6次の繋がりにより、容易に十億単位の人数に達するということを意味します。
カリンティが描いた「15億人の住民」の世界は遠い過去の話であり、今日、世界人口は80億人を突破し、その中で主なSNS利用者数[3]をみてみると、Facebookが約29億6000万人、YouTubeが約25億1000万人、Twitterが約5億6000万人となっています。単純計算で世界人口の3人に1人がSNSを利用している状況[4]にあって、「6次の隔たり」は、いまや「3.5次」あるいは「4.5次」の隔たりにまで縮小しているとの指摘も見られます[5]。
SNSの到来で、誰もが世界中の誰とでも気軽にコンタクトをとれるようになった現在、その利用価値は、個人間のネットワークを超えて、政治・経済・社会などの文脈でさまざまな副次的効果をもたらしつつあるといえます。
不可逆的かつ未曽有の影響力をもつに至ったSNSですが、この新たな社会的インフラには、いうまでもなく機会とリスクの双方を併せ持つ「諸刃の剣」としての特性があります。本稿では、そうしたSNSの二面性に着目しつつ、とりわけ企業の皆様にとって重要なリスクマネジメントの観点から、企業インテリジェンス(Corporate Intelligence)としてのソーシャルリスク対策についてご紹介したいと思います。
[1] 当社調査部による仮訳。
[2] 世界最初のSNSプラットフォームとされる米国のSixDegrees.com(運用期間:1997年~2000年)は、この「六次の隔たり」理論に因んだネーミングです。
[3] 2023年1月の月間利用者数(MAU)。https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
[4] 日本国内については、たとえば総務省が発表した「令和3年度 情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」によれば、現在、SNSの利用者は全人口の約8割で、そのうち10~40歳代の利用率は9割を超えているとされています。
[5] https://www.nytimes.com/2016/02/05/technology/six-degrees-of-separation-facebook-finds-a-smaller-number.html
SNSマーケティングの拡大
SNSが有する拡散効果や利用者間の双方向コミュニケーションなどの特性がもたらした社会的なインパクトは、実にさまざまです。
政治・社会的な文脈では、たとえば2010年から2012年にかけて発生した、いわゆる「アラブの春」におけるSNSの活用がよく知られています。この一連の政治変動を通じて、チュニジアやエジプトでは、反政府運動に参加した民衆がツイッターやフェイスブックなどのSNSを通じて連帯と情報共有を図ったことで政権は退陣に追い込まれ、さらにそうした動きが越境的に拡大したとされています[1]。
一方、SNSがもたらした最大の恩恵としては、やはり経済的な効果は無視できません。とりわけ、企業によるマーケティングの手段として利用が急速に拡大したことは自然の流れといえます。たとえばB to C事業を営む企業や店舗にとっては、SNSを活用した集客効果や口コミなどの宣伝効果を最適化し、自社店舗に消費者の注目を集めることは必須の課題となりつつあります。
そして何より、チラシやカタログ、テレビ・ラジオのCMなど従来の宣伝媒体と比較してSNSが持つ大きな利点は、自社のアカウントへのアクセス数や、閲覧されたページ内容、その拡散状況などを数値化して確認できるインサイト機能があることといえます。その結果、KPI(業績の中間目標)やKGI(業績の最終目標)が設定しやすくなり、定量的な広報戦略の立案がこれまで以上に容易となりました。
こうした流れを背景として、インフルエンサーやYoutuberのような、従来なかった職種の人々が直接・間接に企業の営業活動に参画するようになったほか、個人事業主がSNSを通じて受注するといった新たな営業手法も誕生しました。SNS内部に設立されるコミュニティについても、従来の同好会的な活動目的とは異なる、ビジネスを主眼とした有料のオンラインサロンが百花繚乱の状況にあります。
[1] 実際のところ「アラブの春」におけるSNSの影響力がどの程度「決定的」であったかについては、現在でも専門家の間で議論があります。本稿ではそうした議論には立ち入りませんが、少なくともいくつか当事国では事態の推移のなかでSNSが一定の役割を果たしたことは間違いなさそうです。
ソーシャルリスクの高まり――監視社会化したSNS空間
このように企業にとって心強いマーケティングのアリーナとなったSNSですが、逆に特定の企業や個人が、いわゆる「炎上」のターゲットとなるなど、その影響力がもたらすマイナスの効果も無視できません。
こうしたSNSがもたらすリスクを、わが国では「ソーシャルリスク」と呼ぶことが増えてきました。「ソーシャルリスク」とは、SNSを通じた情報発信、あるいは第三者によるSNS上での告発によって「炎上」を招くリスク、コンプライアンス違反が発覚するリスクを指します。
こうしたリスクが顕在化した背景には、ある種の正義感、あるいは、意図的に「炎上」を引き起こしてアクセス数増加を図るといった目的から、組織の内部不正や表面化していない事件などを次々と告発していくインフルエンサーやウェブ・ジャーナリストなどが複数登場したこと、またそうした告発に過剰に反応するSNS利用者の存在があります。
インフルエンサーやウェブ・ジャーナリストは、自らの情報収集にもとづき主体的に情報発信をすることがほとんどですが、ときに第三者からの依頼を受けて「告発」を代行することもあるようです。たとえば、非正規雇用の増加や終身雇用の減少などにより、労働組合の存在感が低下し、労使交渉が従来ほど従業員の権利保護の役割を果たせずにいる中、問題を抱えた従業員が、発信力のある社外の人物に内部告発を働きかけるといった事例もみられるようになりました。
このほか、WEB上で騒動の渦中にある人物について、限られた情報や画像をもとに、その本名や自宅住所、勤務先、学校あるいは家族の情報まで特定し、WEB上で暴露することを常習的に行う「特定班」と呼ばれる存在も問題視されています。
こうした動きは、日本国内にとどまらず、グローバルに展開される傾向にあります。そうしたなか、とくにわが国の企業にとって無視できないのが、ESG分野に関するグローバルな監視の目です。
たとえば、2006年、国連による「責任投資原則/Principles for Responsible Investment」[1]の提唱を一つの契機として、世界的にESG投資への関心が高まりつつありますが、こうした動きに呼応するかたちで、各国のNGOや環境活動家が、世界の企業の事業活動がもたらす環境への影響やその持続可能性を常時監視し、何か問題を見出せば、SNSなどを通じて大々的に抗議運動を展開する動きも顕著となっています。他方、ESG分野で優れた取り組みや実績を示した企業については好意的な評価を拡散する事例もみられます。
[1] ESG投資の世界的なイニシアティブであり、署名機関はその投資プロセスにおいて、財務情報に加えて、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に関する視点を取り入れることなどが求められます。
責任の所在を問わない「炎上」リスク
このようにSNSの影響力は「諸刃の剣」というべきものです。ことの良し悪しはともかく、こうしたSNSをめぐる近年の傾向は今後も継続、あるいは熾烈化することが予想されます。企業としては、こうしたSNSをめぐる状況を「所与」として、万全の態勢で臨む必要があるといえます。
SNS上における「炎上」について、一部では、「企業のコアサービスの評価に直結するものは深刻だが、コアサービスとは関係のない表層的なものは一時的な影響に留まる」として楽観視する向きもあります。しかしながら、最近でも、ある人気回転寿司店の醤油入れにいたずらをした動画が拡散したことにより、その運営会社の時価総額が一気に160億円も減少した事例(当事者の高校生には6700万円の損害賠償請求がなされました)や、米国の最大手ビールメーカーが、自社商品のプロモーションにトランスジェンダー女性のインフルエンサーを起用したところ、国内保守派による不買運動が拡大し、1ヶ月で売り上げが約26%も減少した事例などが発生しており、いまや「炎上」は、その原因や責任の所在に関係なく、ターゲットとなった企業に無視できない複合的な悪影響を及ぼすこと必至といえます。
これら2つの事例は、「炎上」の原因が、いわば客観視できる「事実」(いたずらやプロモーションといった可視化できる現象)に基づくものといえますが、他方、なんら根拠のないデマやフェイクニュースも、同様に、ターゲットとなった企業に無視しえないリスクを与えることは言うまでもありません。SNSでは、誰もが簡単に情報を発信できる上、誤情報や偽情報も容易に拡散しうる状況にあることから、利用者側も、なにが事実で正確な情報かを判断しにくく、意図せず誤情報や偽情報を引用し、また拡散してしまうケースも多発しています。
企業が「炎上」のターゲットとなった場合、さしあたり以下のリスクが想定されます。
- レピュテーションリスク:
自社のネガティブな風評が拡大し、その信用やブランドが毀損されるリスク
- 利益減少リスク:
消費者が自社の製品やサービスを忌避し、売上が劇的に落ち込むリスク
- 訴訟・賠償リスク:
「炎上」に伴う損害をめぐり訴訟当事者となる、あるいは賠償責任を負うリスク
- 規制リスク:
「炎上」をきっかけに、規制当局の調査対象となり、処分等を受けるリスク
ポスト・トゥルース時代の到来?
ところで、「ポスト・トゥルース(post-truth)」とは、オックスフォード大学出版局が2016年の「ワード・オブ・ザ・イヤー」に選んだ言葉ですが、「世論の形成において、客観的事実の影響力が、感情や個人の信念に対する訴えかけに劣る状況を意味する、またはこのような状況に関する形容詞」と定義されます[1]。
2016年当時、この言葉が注目された背景には、同年の英国のEU離脱をめぐる国民投票や米国の大統領選挙に関する報道を通じて、メディア等が頻繁にこの言葉を用いたことがあります。もっとも「客観的事実の影響力が、感情や個人の信念に対する訴えかけに劣る」という状況は、そうした特定の政治的イベントに限られた現象ではなく、SNS時代の現在、宿命的に私たちの社会を特徴づけているといえます。
もともとデマやフェイクニュースは、真実よりも拡散されやすいとする研究[2]もあり、とりわけ人々の心情に直接訴える内容は、より一層、人々に浸透しやすい傾向にあるといえます。たとえば、東日本大震災やコロナ禍などの非常事態では、不安に襲われた人々が、ひたすら情報を追い求めるあまり、真偽の定かではない情報に飛びつき、それを不用意に拡散してしまうといった事態も数知れず生じました。
2019年に香港で発生した大規模デモをめぐり、900件を超えるFacebookやTwitterの不正アカウントが中国政府による情報操作に使われていたとの調査報告もみられます。現在継続中のロシアによるウクライナ侵攻[3]においても、「情報戦」や「世論戦」が活性化し、こうしたプロパガンダ合戦は「第二の戦場」ともいうべき様相を呈しています。
また近年では、AI生成による質の高いディープフェイク動画などのコンテンツを誰でも簡単に作成できるようになったという技術的な要因も、フェイクニュースの拡散を後押ししていると考えられます。
一般的に、SNS上に出回るデマやフェイクニュースに振り回されないためには、個々の利用者が自身で情報の真偽を確認する「ファクトチェック(事実の検証)」を習慣化することが不可欠です。
そのため、世界各国では、情報の真偽を検証してくれるファクトチェックサイトが開設され、わが国でも、2022年10月、個人がSNSやネットで発信した情報の真偽を独自に調査し、精査記事として公開する「日本ファクトチェックセンター(JFC)」が発足しました。ただし、現状、わが国におけるファクトチェックの普及率は、アジア主要国でも最下位とされる[4]など、全般的に「フェイクニュースに弱い」傾向にあるようです。従って、わが国企業としては、そうした日本人全般の情報リテラシーの脆弱性を考慮しつつ、ソーシャルリスク対策を講じる必要があるといえます。
[1] https://languages.oup.com/word-of-the-year/2016/
[2] 代表的なものとしてMITの情報科学の教授Sinan Aral氏による研究が知られています。
Cf. Aral, Sinan (2020), The Hype Machine, Random House LLC.
[3] 本稿では、当該紛争について、当事国による宣戦布告を伴わないこと、また、第三国に対して、戦時国際法が定める中立義務を発生させていないことなどから、厳密な意味での「戦争」とはみなさず、「侵攻」との表現を用いています。
[4] 2023年6月3日付『日本経済新聞』記事「フェイクニュースに弱い日本 確認法『知る』2割どまり」。
企業インテリジェンスとしてのソーシャルリスク対策
今日の企業は、その一挙手一投足が国内外の不特定多数の「目」の監視下におかれています。また、「炎上」は常に事実に基づくとは限らず、デマやフェイクニュースによっても容易に発生し、特定の企業や個人のイメージを意図的に下げることを目的としたネガティブキャンペーンもさまざまな動機で展開されます。他方、企業側の不用意な情報発信が、「炎上」の直接の原因となることも少なくありません。
こうしたソーシャルリスクを未然に防ぐ、あるいはひとたび「炎上」等のインシデントが発生した場合には冷静かつ効果的に対処することがSNS時代における企業インテリジェンスの大きな課題となります。
- 事前対応
あらゆるソーシャルリスクの要因を未然に根絶することは困難ですが、「炎上」の潜在的要因を事前に低減させる、あるいは早期に探知することは可能です。
ソーシャルリスクに対する事前対応は、大きく、社内的対応と社外的対応に整理されます。社内的対応には、社員・アルバイトなどによるSNS等での不用意な情報発信を未然に防ぐためのガイドラインや罰則規定の策定、顧客のクレーム対応マニュアルの拡充(適切なフォローアップによる「告発」の抑止)、インシデント対応時の作業手順の整備などが含まれます。
社外的対応には、SNS等のWEBモニタリングの定期化(不穏な投稿の抽出)、インフルエンサー・WEBジャーナリストとの関係構築、潜在的脅威となる組織や人物の特定と警戒、などが含まれます。
- インシデント対応
ひとたび、インシデントが発生した場合、次のような対応が効果的とされます。
事前に整備していた作業手順に沿って、迅速かつ適切な「火元」の特定と効果的な「火消し」を行う必要があります。具体的には、ソーシャルリスニング(ソーシャルメディア上で交わされるユーザー間のやりとりの収集・分析)を通じた状況の把握と、「火元」情報の保存・記録、「火元」の投稿者の情報収集、サジェスト対策(検索エンジンにおいて特定のサジェストワードを表示あるいは非表示とする)などが含まれます。
- 事後対応
インシデントが一定程度、収束した段階で、適切な事後対応が必要となります。具体的には、被害状況の整理、法的責任の所在確定、法的措置、企業イメージの回復オペレーションなどが含まれます。
こうした事後対応のためには、SNS情報を含むWEB上で確認できる情報の検証、敵対的行動をとる人物や組織の把握と動機の精査など、多角的な観点からの情報収集と分析がなにより重要となります。
ソーシャルリスク対策のカギとなるOSINTツール
ソーシャルリスクへの3段階での対応において情報収集・分析の側面で効果を発揮するのが、OSINTと呼ばれる調査手法です。OSINTとは「Open Source Intelligence(オープンソース・インテリジェンス)」の略称で、マスメディアによる報道、WEB上の記事・新聞・書籍などの合法的に入手可能な公開情報を収集・分析するインテリジェンスプロセスを指す用語です。いうまでもなく、公開情報では、SNSが占める情報量も着実に増加傾向にあります。
OSINTは、歴史が実に長く、また裾野の広い活動でありますが、近年は、従来の人間の五感を駆使した作業に加えて、さまざまデジタル技術を活用したOSINTツールや、生成AIを基盤とするWEBインテリジェンスツールなどの開発が進み、SNSなどWEB空間における情報収集・分析のスピード、精度、奥行きなどが劇的に向上しています。
OSINTツールはさまざまな機能のものがあり、WEB情報のリアルタイムのデータマイニングや情報収集はもちろんのこと、メールアドレスの流出状況の検出、ダークウェブ上での個人情報流出を検出、特定のSNSアカウントにおける「つながり」の状況や投稿内容のリスト化・分析、「いいね!」やコメント数による親密度の測定など、調査の目的によって、適材適所に使用することができます[1]。
こうしたOSINTツールを駆使したソーシャルリスク対策は、さらに「炎上」やネガティブキャンペーンの背後にいる組織や人物の特定、動機の把握などを目的とした、従来型のOSINTを通じた調査と組み合わせることによって効果を発揮します。
ソーシャルリスクは、SNSを舞台したデジタル技術を背景とする最新の現象であるとともに、人間のデマやフェイクニュース等へのリテラシーの脆弱性、特定の組織や個人のイメージを毀損しようと企む人間感情、そのほか、匿名の立場で騒動を愉しもうとする集団心理など複合的な要素から成り立つリスクです。
そうした複合的なリスクには、同じく複合的な観点からの情報収集・分析で対応する必要があります。当社は企業のリスクマネジメントを専門的に支えるインテリジェンスカンパニーとして、お客様のソーシャルリスク対策をサポートいたします。
[1] 以前は、有志が作成した解析ツールが複数、WEB上で無料で提供されていましたが、最近はSNSのAPI(Application Programming Interface)の仕様の変更などによって、提供が停止されたツールが増えています。
この記事の執筆者